レフカディオ・ヘブンがついに松江へ!運命の出会いが始まる
NHK連続テレビ小説「ばけばけ」第21話では、ついに物語の重要人物であるレフカディオ・ヘブンが松江に上陸しました。銀二郎との別れから4年が経過し、22歳になったトキは、しじみ売りと内職で家計を支える日々を送っていました。借金生活から抜け出せない苦しい状況の中、松江に初めての外国人がやってくるという知らせが届きます。
松江中学の英語教師として赴任することになったレフカディオ・ヘブン。彼の到着は、当時の松江にとってまさにビッグイベントでした。トキは親友のサワと共に船着き場へ向かい、初めて見る外国人に胸を躍らせます。船から降りてきたヘブンの姿を見たトキは「天狗だ!」と大興奮。その高い鼻と異国の風貌に、怪談好きのトキの心は一気に引き寄せられていきました。
花田旅館の主人夫妻との会話では、外国人についての様々な噂が飛び交います。鼻が高くて顔が赤くて空を飛ぶ特徴を「天狗」、お皿があってキュウリが好きなら「河童」、角があれば「鬼」と、トキが次々とツッコミを入れる場面は、視聴者にも笑いを届けました。この軽快なやり取りは、脚本を手がけるふじきみつ彦氏がコント作家としての経験を持つことからも納得できる展開です。
船着き場には大勢の人々が集まり、まるでアメリカ大統領が来日するかのような歓迎ぶりでした。新聞記者の梶谷は「100万を超える大群衆の歓迎」とオーバーな記事を書く始末。実際には数百人程度だったと思われますが、当時の地方都市にとって外国人の来訪がいかに特別なことだったかが伝わってきます。江藤県知事をはじめ、松江の有力者たちが総出で出迎える様子からも、ヘブンへの期待の大きさが感じられました。
しかし、船から降りてきたヘブンの表情には、どこか疲れや不安の影が見え隠れしていました。前屈みの姿勢や時折見せる暗い表情は、長い船旅の疲れだけではない何かを感じさせます。アメリカの新聞社から日本へ取材に来たはずが、なぜ英語教師として赴任することになったのか。その経緯はまだ明かされていません。
トキにとって、このヘブンとの出会いは人生を大きく変える転機となります。銀二郎を「小豆洗い」と例えたトキですが、ヘブンは正真正銘の「天狗」。怪談を愛してやまないトキの心に、運命の人が現れた瞬間でした。船上のヘブンに向かって懸命に手を振り続けるトキの姿には、これから始まる物語への期待が込められています。
当時の松江では、外国人は「異人」と呼ばれ、畏怖と好奇心の対象でした。勘右衛門のように攘夷思想を持つ人物もいれば、トキのように純粋に興味を示す人々もいました。このような多様な反応が交錯する中で、レフカディオ・ヘブンと松野トキの物語が幕を開けたのです。二人の初対面がどのような形で実現するのか、そしてどのように心を通わせていくのか、今後の展開から目が離せません。

錦織友一の再登場で物語が動き出す予感
第21話では、吉沢亮演じる錦織友一が4年ぶりに松江に戻ってきました。トキが船着き場を訪れた際、通訳として登場した錦織との再会は、視聴者にとっても嬉しいサプライズとなりました。東京編が終了したことで退場したかと思われた錦織でしたが、レフカディオ・ヘブンの通訳という重要な役割を担って物語に復帰したのです。
錦織は以前、帝国大学の試験に合格して東京から松江を近代化すると語っていました。優秀な青年として期待されていた彼が、なぜわずか4年で松江に戻ってくることになったのか。その理由については劇中でまだ明確に語られていません。松江に到着した際、錦織の表情にはどこか浮かない影が見られました。もしかすると、試験の結果が芳しくなかったのかもしれません。
優秀であれば東京で通訳や教師の仕事を依頼されたはずです。しかし彼は地方である松江での通訳という役割に就いています。これは都落ちとも取れる状況で、錦織自身も複雑な心境を抱えているように見えました。江藤県知事に呼ばれて英語が話せる人材として重宝されているものの、本人の志とは異なる道を歩んでいる可能性があります。
それでも錦織は、トキとの再会では明るく「ワオ」と声を上げて応じていました。トキのことを覚えていて、親しげに接する様子からは、彼の人柄の良さが伝わってきます。4年という時を経ても変わらない優しさを持ち続けている錦織の存在は、これからのトキの人生において重要な役割を果たすことになるでしょう。
錦織の役割は単なる通訳にとどまらないと考えられます。レフカディオ・ヘブンと松江の人々を繋ぐ架け橋として、また西洋文化と日本文化の間に立つ調整役として、彼の存在は不可欠です。特にトキとヘブンの関係が深まっていく過程で、錦織がどのような立場で関わっていくのか注目されます。
SNS上では「錦織さんとの再会は嬉しかった」「トキのこと覚えてたね」といった好意的な声が多数寄せられました。吉沢亮の人気もあって、彼の再登場は視聴者のボルテージを一段と高めることになりました。東京での経験を経て成長した錦織が、今後どのような活躍を見せるのか期待が高まります。
また、錦織がアメリカにいたヘブンをどのようにして知り、なぜ彼の通訳として松江に呼ばれることになったのかも謎のままです。ヘブンがアメリカの新聞社で取材のために日本行きを決めた経緯は描かれましたが、それが英語教師という職業に変わった理由は不明です。この背景には錦織が関わっている可能性もあり、二人の関係性が今後明らかになっていくでしょう。
錦織の存在は、トキとヘブンの物語を支える重要な柱となります。言葉の壁を超えて心を通わせようとする二人を見守り、時には助言を与える存在として、彼の役割は大きくなっていくはずです。明治という激動の時代に、新しい価値観を受け入れながら生きる若者たちの姿が、これから丁寧に描かれていくことでしょう。
ラシャメンという言葉が示す明治時代の複雑な背景
第21話では「ラシャメン」という言葉が登場し、視聴者に明治時代の社会背景を伝える重要な要素となりました。ラシャメンとは「洋妾」を意味する言葉で、西洋人の妾となった日本人女性を指します。遊郭で働くなみは、レフカディオ・ヘブンのラシャメンになることを目指し、サワに英語を教えてもらっていました。
当時、ラシャメンは多額の給金をもらえることで知られていました。日本に来る西洋人、特にお雇い外国人と呼ばれた人々は、日本人には手が届かないような高給取りでした。ヘブンの年収は県知事に次ぐ100円とされ、後に東京帝国大学の講師を務めた際には400円もの収入を得ていたといいます。このような経済的な魅力から、困窮した女性たちの中にはラシャメンになることを選ぶ者もいました。
しかし、ラシャメンは経済的には恵まれていても、社会的には日本人の妾以上に蔑まれる存在でした。西洋人と関係を持つことへの偏見や、高給への嫉妬が入り混じり、周囲から白い目で見られることが常だったのです。トキのモデルである小泉セツも、後年に次男の妻に対して「洋妾、洋妾」と周りから言われることが一番辛かったと語ったといいます。
劇中で勘右衛門は、なみがラシャメンになりたいと聞いて激怒し、「であえ、であえ」と叫びながら子供たちと共に追いかけ回していました。攘夷思想を持つ勘右衛門にとって、外国人と関係を持つことは許しがたい行為だったのです。この場面は、当時の保守的な価値観を持つ人々の反応を象徴的に表現していました。
一方で、なみ本人は「わたしラシャメンになるわよ」と張り切っている様子でした。これは単なる経済的理由だけでなく、遊女という立場から抜け出し、より良い生活を手に入れたいという願望の表れでもあったでしょう。当時の女性たちにとって、自分の人生を切り開く選択肢は極めて限られていました。
この「ラシャメン」という設定は、視聴者に対して重要な情報を伝える役割を果たしています。トキがヘブンの元に女中として住み込み、やがて妻となることが、周囲にどのように受け止められるかを予告しているのです。正式な結婚であっても、外国人の妻となったトキは「ラシャメン」と見なされ、偏見にさらされる可能性が高いのです。
歴史的には、幕末の開港地でよく使われた言葉でしたが、明治20年代の松江でもまだこの言葉が使われていたことが分かります。サザンオールスターズの「唐人物語(ラシャメンのうた)」という曲のモデルとなった斎藤きち(唐人お吉)も、ハリスの看病をしただけでラシャメンと呼ばれ、いわれのない差別を受けて悲劇的な最期を遂げました。
トキとヘブンの物語は、このような偏見と戦いながら、真実の愛を育んでいく過程でもあります。二人が社会の壁をどのように乗り越えていくのか、そして勘右衛門をはじめとする周囲の人々がどのように変化していくのか。ラシャメンという言葉が示す複雑な社会背景を理解することで、これから描かれる物語の深みがより一層増していくことでしょう。
松江を舞台に描かれる新たな章の幕開け
第21話から物語の舞台は本格的に松江へと移りました。1890年(明治23年)の松江は、まだ外国人を見たことがない人々がほとんどという時代でした。レフカディオ・ヘブンの到着は、この地方都市にとって歴史的な出来事となり、街全体が沸き立つような興奮に包まれました。
松江の船着き場に集まった人々の姿からは、当時の日本社会の様子が鮮明に伝わってきます。女性はまだ着物に日本髪という伝統的な装いで、男性は着物と洋服が混在し、髪型はざん切り頭が主流でした。髷を結っているのは勘右衛門だけという描写は、彼が「江戸時代の化石」のような存在であることを象徴していました。
トキの生活も松江という土地に根ざしたものでした。宍道湖のしじみ売りで生計を立て、花田旅館に出入りしながら、夜は内職に励む日々。1合のしじみが2銭で、仕入れ値を差し引くと日給は10銭から20銭程度。司之介の牛乳配達と合わせても、月収は15円から18円ほどにしかなりません。300円の借金に対して月利3%では、利息が返済額を上回ってしまう厳しい状況でした。
それでも松野家の人々は明るさを失わず、井戸に落ちた小銭を拾おうとする司之介とフミの姿には、貧しくも前向きに生きる家族の姿が描かれていました。この井戸から千両箱が出てくるという話は、後にヘブンの存在を暗示するものとなっていくのでしょう。
松江という土地柄も物語に重要な影響を与えています。松江城には人柱の祟りという怪談が伝わり、怪談好きのトキにとっては興味深い場所です。この地の持つ神秘的な雰囲気と、トキの怪談への情熱が、やがてヘブンとの共通点となっていきます。小泉八雲が日本の怪談を世界に紹介した作家であることを考えると、松江という舞台設定は物語にとって必然的なものでした。
花田旅館の主人夫妻である生瀬勝久と池谷のぶえの登場も、松江編の新たな魅力となっています。二人の漫才のようなやり取りは、視聴者に笑いを提供しながら、トキの日常を支える温かい人間関係を表現していました。「こげに働いて私は銀二郎かい」というトキの自虐的なツッコミも、脚本家のコント作家としての才能が光る場面でした。
島根県知事の江藤を演じる佐野史郎も、松江出身の俳優として物語に深みを添えています。外国人教師を招聘する役割を担う江藤の存在は、当時の地方行政が近代化に向けてどのように動いていたかを示す重要な要素です。鳥取県が松平家で中央から睨まれていたという背景もあり、外国人教師の来日は地方にとって大きな意味を持つイベントでした。
新聞記者の梶谷がオーバーな記事を書く様子も、地方メディアの特性を表現していました。「100万人の大群衆」という誇張された表現は、松江という地方都市が自分たちの街を盛り上げようとする姿勢を象徴しています。このようなカオス的な雰囲気の中で、トキとヘブンの運命的な出会いが始まろうとしているのです。
松江を舞台とした新章は、登場人物たちの新たな関係性と、明治という時代の空気を丁寧に描き出しています。トキが「天狗だ」と喜びの表情を見せながらヘブンに手を振る姿は、これから始まる二人の物語への期待を高めました。怪談を愛する夫婦の日常が、この松江という土地でどのように紡がれていくのか、今後の展開が楽しみです。



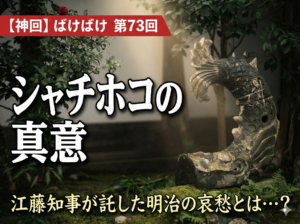


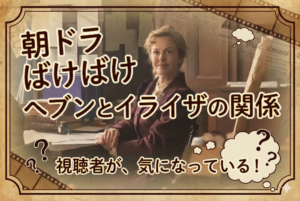
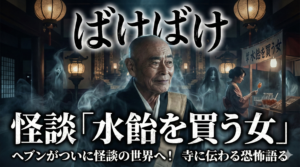


コメント