2025年9月29日から放送が開始されたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、明治時代を舞台に小泉八雲の妻である小泉セツをモデルとした物語として、多くの視聴者の心を捉えています。ドラマの約70パーセントが松江市を舞台としており、松江市内の各所でロケが行われたことから、松江市は聖地巡礼の観光地として再び脚光を浴びています。特に注目を集めているのが、小泉八雲記念館とその隣に位置する小泉八雲旧居です。これらのスポットはドラマのオープニング映像にも登場し、実際にロケ地として使用されました。松江城や八重垣神社、宍道湖など、松江市内には「ばけばけ」のロケ地が数多く存在し、それぞれが小泉八雲とセツの足跡を今に伝えています。本記事では、松江市の小泉八雲記念館を中心に、ドラマ「ばけばけ」のロケ地について詳しくご紹介します。明治という激動の時代を生き抜いた女性の物語と、その舞台となった松江の魅力を、ぜひご堪能ください。

朝ドラ「ばけばけ」の魅力と物語の背景
「ばけばけ」は、2025年9月29日から放送が開始されたNHK連続テレビ小説第113作で、全125話が予定されています。この作品は原作のないオリジナル脚本による作品として制作されており、明治時代という時代背景の中で、小泉八雲の妻である小泉セツをモデルとした物語が展開されています。
物語の主人公である松野トキは、松江藩の武家の家に生まれました。しかし、明治維新による武士階級の解体により家が没落し、わずか11歳から織物職人として働き始めることになります。この過酷な環境の中でも、トキは真面目に働き、家族を支えていきました。18歳のときに結婚しますが、夫は貧しさに耐えられず1年で家を出てしまいます。経済的な困窮と将来への不安から、夫が逃げるように去ってしまったという現実は、トキにとって大きな試練となりました。
その後、1886年に英語教師として松江にやってきたラフカディオ・ハーン、劇中ではヘブンという名前で登場する人物の住み込みの手伝いとして働き始めます。トキは日本の文化や風習、言葉をヘブンに教える役割を果たし、二人は次第に心を通わせるようになりました。当時としては極めて珍しい国際結婚に至った二人の物語は、文化や言葉の壁を超えた真の愛を描いています。
トキは語り部として口承文学を語り聞かせ、夫の作品づくりに大きく貢献していきます。このドラマが描くのは、単なる夫婦の愛の物語だけではありません。明治という激動の時代を生き抜いた女性の強さ、そして文学作品を共に創り上げていく創作の喜びが、物語の中心となっています。
主演は一般公募で2892人の応募者の中から選ばれた髙石あかりさんが務めます。初々しさと芯の強さを併せ持つトキを熱演しており、視聴者から高い評価を受けています。ヘブン役には、1767人の応募の中から選ばれたイギリス人俳優のトミー・バストウさんが抜擢されました。トミーさんは日本文化に深い関心を持つ外国人教師を説得力を持って演じており、その演技力が光ります。
ドラマには他にも、吉沢亮さん、北川景子さん、堤真一さん、小日向文世さん、池脇千鶴さん、生瀬勝久さんなど、実力派俳優が多数出演しています。特に注目すべきは、松江出身の俳優である佐野史郎さんが島根県知事の江藤安宗役で出演していることです。佐野さんは小泉八雲記念館の音声展示にも参加されており、ドラマと記念館の両方で八雲の世界を伝える役割を担っています。
小泉八雲記念館の魅力と展示内容
小泉八雲記念館は、島根県松江市奥谷町に位置する博物館で、松江城から徒歩約10分の距離にあります。城下町の一角に位置しており、小泉八雲旧居の隣に建てられているため、両施設を合わせて見学することで、八雲の世界をより深く理解することができます。
この記念館は2016年夏に展示構成を拡充・一新し、ライブラリーやホール、ミュージアムショップを備えた記念館として生まれ変わりました。館内には直筆原稿や初版本のほか、愛用の机、椅子、衣類などの遺愛品を中心に、百数十点以上が展示されています。これらの展示品は、八雲の生涯と作品世界を知る上で貴重な資料となっています。
第1展示室では、「その眼が見たもの」「その耳が聞いたもの」「その心に響いたもの」というコンセプトのもと、小泉八雲の生涯を編年で紹介しています。時系列に沿って八雲の足跡をたどることができ、来館者は八雲がどのような人生を歩んだのかを深く理解することができます。1850年にギリシャのレフカダ島で生まれ、複雑な生い立ちを経験した八雲が、1890年に39歳で初めて日本を訪れ、松江で人生の転機を迎えるまでの道のりが丁寧に展示されています。
第2展示室では、八雲の事績や思考の特色を、「再話」「クレオール」「いのち」など8つの切り口から描き出しています。八雲の作品世界や思想を多角的に理解できる構成となっており、単なる伝記展示にとどまらない深い内容が魅力です。八雲が日本の民話や伝説を西洋文学の手法で再構成し、世界に通用する文学作品として昇華させた過程を、様々な視点から学ぶことができます。
特に注目すべき展示の一つが、『怪談』『日本―ひとつの解明』を書いた東京・西大久保の自宅の書斎の再現です。遺愛の品々によって当時の雰囲気が忠実に再現されており、八雲が執筆活動に没頭していた空間を体感することができます。愛用の机と椅子は特注品で、視力が悪かった八雲のために作られたものです。このような細部にまで八雲の生活や人となりを知ることができる展示が充実しています。
また、館内では松江出身の俳優・佐野史郎さんとギタリスト・山本恭司さんが紡ぎ出す八雲の世界を音声で楽しむことができます。第2展示室で聴くことができるこの音声展示は、八雲の作品世界をより深く感じられる演出となっており、訪れた人々に深い感動を与えています。佐野さんの朗読は、八雲の文学作品が持つ幻想的で哀愁に満ちた雰囲気を見事に表現しており、必聴の価値があります。
ライブラリーには八雲関連の書籍が豊富に揃っており、自由に閲覧することができます。研究者だけでなく、一般の観光客も八雲の作品に触れることができる開かれた空間となっています。ミュージアムショップでは、八雲の著作や関連グッズを購入することができ、松江観光の思い出として持ち帰ることができます。
小泉八雲旧居とドラマのロケ地としての魅力
小泉八雲旧居は、現在一般公開されており、小泉八雲記念館のすぐ隣に位置しています。この旧居は「ばけばけ」のロケ地として使用され、ドラマのオープニング映像にも登場しています。ドラマファンにとっては、作品の世界観を実際に体感できる貴重なスポットとなっており、多くの観光客が訪れています。
旧居の室内から庭を眺める映像は、「ばけばけ」のオープニングで使用されています。主人公のトキとヘブンが座っている場面や、机に向かっている場面も、この旧居で撮影されました。実際に訪れてみると、ドラマで見た風景がそのまま目の前に広がり、感動を覚えることでしょう。ドラマの撮影が行われた場所に立つことで、トキとヘブンが過ごした時間を追体験することができます。
ポスタービジュアルに映り込んでいる法螺貝は、実際に旧居に展示されている品物です。ドラマを見てから旧居を訪れると、「あの法螺貝はここにあったのか」という発見があり、より深くドラマの世界に浸ることができます。このような細部にまでこだわった展示が、旧居の魅力を高めています。
旧居内部には当時の生活の様子を伝える展示があり、八雲とセツが過ごした空間を実際に見学することができます。八雲が松江で過ごした期間はわずか1年3カ月でしたが、この短い期間が八雲の人生において決定的な意味を持つ時間となりました。旧居を訪れることで、この地で八雲とセツがどのように暮らし、どのように心を通わせていったのかを実感することができます。
庭園も美しく保存されており、四季折々の風情を楽しむことができます。特に春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、季節ごとに異なる表情を見せる庭は、何度訪れても新しい発見があります。八雲もこの庭を愛し、日本の自然の美しさに深い感銘を受けたことでしょう。
旧居の縁側に座って庭を眺めると、時間がゆっくりと流れているような感覚を味わえます。現代の喧騒から離れ、明治時代にタイムスリップしたような静寂の中で、八雲とセツの物語に思いを馳せることができる貴重な空間です。
八重垣神社でのロケと縁結びのパワースポット
八重垣神社は松江市佐草町に位置する神社で、縁結びのパワースポットとして全国的に知られています。「ばけばけ」の第5回では、主人公のトキが鏡の池で恋占いを行うシーンが撮影されました。この場面は、トキの恋心や将来への希望を象徴する重要なシーンとして、多くの視聴者の印象に残っています。
実際のロケは2025年5月21日から22日にかけて行われました。興味深いことに、歴史上の小泉セツ自身も、若い頃にこの池で恋占いを行ったという記録が残っています。ドラマの中でトキが行った恋占いは、実際にセツが体験したことを再現したものであり、史実に基づいた演出となっています。
八重垣神社の鏡の池では、紙に硬貨を乗せて池に浮かべ、紙が沈む速さや場所で恋の行方を占う「縁占い」が有名です。紙が早く沈めば恋の成就も早いとされ、遠くに流れていけば遠方の人とのご縁、近くで沈めば身近な人とのご縁があるとされています。この占いは現代でも多くの観光客が体験しており、特に若い女性や恋人同士に人気があります。
神社の境内は静かで神聖な雰囲気があり、心が洗われるような感覚を味わえます。古くから縁結びの神様として信仰を集めてきた八重垣神社は、出雲神話とも深い関わりがあります。素戔嗚尊が八岐大蛇を退治し、救った稲田姫命と結婚したという神話の舞台として知られており、この神話から縁結びの神社として崇敬されるようになりました。
「ばけばけ」のロケ地として訪れる観光客も増えており、ドラマのシーンを思い出しながら鏡の池で恋占いを体験する人々の姿が見られます。トキがこの場所で未来への希望を抱いたように、訪れる人々も自分の恋の成就を祈願しています。
松江城とその周辺のロケ地
松江城は、島根県松江市殿町に位置する城で、天守が現存する12城の一つとして国宝に指定されています。1611年に完成した松江城は、400年以上の歴史を持ち、その威風堂々とした姿は今も松江市のシンボルとして市民に愛されています。
「ばけばけ」では、内堀にかかる宇賀橋という木造の橋が登場します。ドラマでは、夫婦が赤い傘をさして橋を渡るシーンが撮影されました。この赤い傘は、雨の中でも二人が寄り添いながら歩む姿を象徴しており、視覚的にも美しいシーンとして視聴者の記憶に残っています。
宇賀橋は松江城の内堀を渡る橋の一つで、木造の趣ある橋です。橋の上からは松江城天守を眺めることができ、絶好の撮影スポットとなっています。特に桜の季節や紅葉の季節には、城と橋と自然が織りなす美しい風景を楽しむことができます。
松江城自体も武家時代の象徴としてドラマに登場し、城下町の風情を演出しています。天守からの眺めは絶景で、松江市内を一望することができます。宍道湖や市街地、遠くの山々まで見渡せる景色は、訪れる価値のある素晴らしいものです。
松江城の北側、塩見縄手と呼ばれる地域は、堀に沿って武家屋敷が並ぶ松江で最も城下町らしい雰囲気を残す場所です。この地域は伝統的建造物群保存地区に指定されており、小泉八雲旧居と記念館もこの通り沿いにあります。江戸時代の面影を残す美しい通りを散策することで、タイムスリップしたような感覚を味わえます。
塩見縄手を歩くと、武家屋敷の黒板塀が続き、静かで落ち着いた雰囲気が漂っています。この通りは「日本の道百選」にも選ばれており、松江観光のハイライトの一つとなっています。八雲とセツもこの道を歩いたことでしょう。当時の面影を今に伝える貴重な景観です。
月照寺と城山稲荷神社でのロケ
「ばけばけ」では、松江市内の複数の寺院や神社がロケ地として使用されています。月照寺は、松江藩主松平家の菩提寺で、歴史ある建築物や庭園が見どころです。小泉八雲も訪れたことがあり、怪談の舞台としても知られています。
月照寺には大亀の伝説があり、八雲はこの伝説に興味を持ったとされています。境内には松平家歴代藩主の墓所があり、それぞれの墓には石灯籠が並んでいます。この石灯籠にまつわる怪談が、八雲の作品のインスピレーション源となったといわれています。静寂に包まれた境内は、怪談の舞台にふさわしい神秘的な雰囲気を漂わせています。
城山稲荷神社では、2025年に髙石あかりさんとトミー・バストウさんが出席する松江ロケ報告会が開催されました。この報告会では、二人が松江でのロケの思い出や、ドラマへの思いを語り、多くのファンが集まりました。城山稲荷神社も小泉八雲と妻セツゆかりの地として知られており、ドラマのロケ地巡りには欠かせないスポットとなっています。
これらの寺院や神社は、ドラマのロケ地としてだけでなく、八雲の文学作品と深い関わりを持つ場所です。八雲は松江滞在中にこれらの場所を訪れ、日本の宗教文化や精神性に触れました。その体験が、後の作品づくりに大きな影響を与えたことは間違いありません。
宍道湖の美しい夕日と「ばけばけ」の風景
宍道湖は松江市と出雲市にまたがる汽水湖で、夕日の名所として全国的に有名です。「ばけばけ」のオープニング映像でも宍道湖の美しい風景が使用されており、松江の象徴的な風景として描かれています。ドラマを見た多くの視聴者が「松江って素敵な街ですね」という感想を寄せており、その多くが宍道湖の美しさに魅了されています。
宍道湖の夕日は「日本の夕日百選」にも選ばれており、特に嫁ヶ島のシルエットと夕日が織りなす光景は格別です。夕暮れ時になると、空と湖面がオレンジ色や紅色に染まり、幻想的な風景が広がります。この美しい夕日を一目見ようと、多くの観光客が湖畔に集まります。
八雲とセツも、この湖畔を散策したことでしょう。八雲は松江を「神々の国の首都」と表現し、この地に対する深い愛情を示しました。宍道湖の夕日は、八雲が松江の美しさを讃えた理由の一つであったに違いありません。
宍道湖畔には夕日スポットが整備されており、美しい夕景を眺めながらゆったりとした時間を過ごすことができます。ベンチに座って夕日を眺めていると、日常の喧騒を忘れ、心が穏やかになっていくのを感じます。ドラマ「ばけばけ」の世界観を思い出しながら、この美しい風景を楽しむのは、松江観光の醍醐味の一つです。
小泉八雲とラフカディオ・ハーンの生涯
小泉八雲は1850年、ギリシャのレフカダ島で生まれました。本名はパトリック・ラフカディオ・ハーンといいます。アイルランド系の父とギリシャ人の母の間に生まれましたが、幼少期に両親が離婚し、複雑な生い立ちを経験しました。この複雑な生い立ちが、八雲の感性を研ぎ澄まし、異文化への深い理解と共感を育てたといわれています。
1890年、明治23年、39歳のときに取材で初めて日本を訪れました。その後、新聞社を離れて英語教師となり、島根県尋常中学校に赴任します。日本での生活は14年間にわたりましたが、松江で過ごした期間はわずか1年3カ月ほどでした。しかし、八雲にとって松江は家族を得ることができた大切な場所となりました。
松江での生活を始めた八雲は、知人の紹介で士族の娘・小泉セツと出会います。セツは八雲の身の回りの世話や日本文化の案内役を務めるようになり、やがて2人は親しくなり、1891年に結婚しました。当時、国際結婚は極めて珍しく、周囲からの偏見もありましたが、二人は互いを深く理解し尊重し合う関係を築いていきました。
八雲は日本語の読み書きがあまりできなかったため、妻のセツが民話や怪談を語って聞かせました。セツの語りは八雲の創作活動にとって欠かせないものとなり、『怪談』に代表される後年の再話文学の多くが、セツの語りから生み出されていきました。八雲は研ぎ澄まされた五感で日本文化の本質を捉え、西洋に日本を紹介する作家として活躍しました。
日本人以上に日本の心を理解し、その魅力を世界に伝えた功績は大きく評価されています。八雲の作品は、失われゆく日本の面影を記録し、日本文化の本質を西洋に伝える重要な役割を果たしました。鋭い観察力と感性によって捉えられた日本の姿は、日本人自身も気づかなかった日本の美しさや深さを教えてくれます。
1904年に八雲が54歳で亡くなった後、セツは夫の作品の普及に努めました。また、ハーンとの生活を綴った回想録も残しており、八雲の人となりや二人の生活を知る貴重な資料となっています。
小泉八雲の代表作『怪談』の世界
『怪談』は、小泉八雲が著した怪奇文学作品集で、1904年に出版されました。八雲の妻である節子から聞いた日本各地に伝わる伝説、幽霊話などを再話し、独自の解釈を加えて情緒豊かな文学作品としてよみがえらせたものです。
代表的な作品として「耳なし芳一」があります。これは平家の怨霊に取り憑かれた琵琶法師の物語で、芳一が平家の亡霊たちの前で琵琶を弾く場面は、幻想的で哀愁に満ちた名場面として知られています。僧侶が芳一の体に経文を書いて亡霊から守ろうとしますが、耳だけに経文を書き忘れてしまい、耳だけが亡霊に持ち去られてしまうという展開は、恐怖と悲哀が入り混じった印象的な物語です。
「雪女」は、雪の夜に現れる美しくも恐ろしい妖怪の物語です。人間の男性との間に芽生える愛と、雪女の宿命が描かれています。雪女が正体を明かしてはならないという約束を破られたときの悲しみと怒りは、読者の心に深く残ります。日本の四季や自然への畏敬の念が感じられる作品です。
「むじな」は、化け物が人を化かす短編です。簡潔ながらも背筋が凍るような恐怖を描いています。夜道で出会った人物が実は化け物だったという展開は、シンプルでありながら強烈な印象を残します。
これらの作品は、単なる怪談にとどまらず、日本の美意識や死生観、人間の心理を深く掘り下げた文学作品として評価されています。八雲は日本の民話や伝説を、西洋文学の手法を用いて再構成し、世界に通用する文学作品として昇華させました。
『怪談』の多くが、セツの語りから生み出されたことを考えると、セツは単なる助手ではなく、共同制作者としての役割を果たしていたといえます。セツは家族を支えながら、夫の創作活動を支え続けました。八雲はセツについて、「私には学歴がない」と恥じるセツに対して、完璧な返答をしたとされています。セツの語りや知識が、八雲の作品にとってかけがえのないものであったことを示すエピソードです。
小泉八雲のその他の名作
『知られぬ日本の面影』は、小泉八雲が日本に来て初めて著した作品集で、1894年に出版されました。「知られざる日本の面影」「日本瞥見記」とも呼ばれています。この作品集は、西洋人の視点から見た明治初期の日本の姿を描いた紀行文学です。八雲が初めて日本を訪れたときの新鮮な驚きと感動が、生き生きとした筆致で綴られています。
『知られぬ日本の面影』の中でも特に有名な作品が「神々の国の首都」です。これは出雲の国、松江の朝の情景から、美しい夕日が頂点となり、その余韻を楽しみながら眠りにつくまでを描いた作品です。八雲は松江を「神々の国の首都」と表現し、この地に対する深い愛情を示しました。
八雲の観察は、人々の日常生活に入り込み、その心を理解しようと深く試みる姿勢と、新鮮な感動とが相まって、卓越した文学作品へと昇華されています。「神々の国の首都」「杵築―日本最古の神社」「日本人の微笑」など11編が選ばれた新編も刊行されており、現在も多くの読者に親しまれています。
八雲の作品に描かれた明治時代の日本の姿は、現代ではすでに失われてしまったものも多く、貴重な記録として価値があります。八雲が捉えた日本人の精神性、自然との調和、美意識などは、現代の私たちが改めて見つめ直すべき日本の本質を示しています。
小泉セツの波乱に満ちた人生
小泉セツは、1868年、慶応4年2月4日に松江藩士の家に生まれました。節分生まれであったことから「セツ」と名付けられました。松江藩の家老職を務めた小泉家の次女として生まれましたが、生後わずか7日で稲垣家に養子に出されました。
稲垣家は、松江藩で百石を与えられていた「並士」の家柄でした。小泉家が上士の家柄であるのに対し、それより一段下がる身分でしたが、稲垣金十郎・トミ夫妻は子どもを一人も授かっていなかったため、小泉家との間で次に生まれる子を養子にもらう約束が交わされていました。
養母トミは、幼いセツに出雲神話をはじめ様々な説話を語って聞かせました。この経験が、後にセツが語り部としての才能を発揮する上で大きな影響を与えることになります。トミの語りは、セツの心に深く刻まれ、八雲に物語を語る際の礎となりました。
稲垣家では、セツは「お嬢」としてかわいがられて育ちました。養父母はセツを大切に育て、できる限りの教育を受けさせようとしました。セツは聡明で、飛び級するほど優秀な成績を収めていました。しかし、養父の事業が失敗したことにより、セツは小学校を中退せざるを得なくなりました。学ぶことが好きだったセツにとって、これは非常に悔しい出来事で、涙を流したといいます。
明治維新により武士階級が解体されたため、稲垣家も経済的に困窮しました。稲垣家の男性陣は時代の変化に適応できなかったため、実直で真面目に働く養母トミとセツが生計を担っていくことになります。家計を支えるため、セツは11歳から織物職人として働き始めました。幼い手で機を織る日々は過酷でしたが、家族のためにセツは懸命に働きました。
セツが18歳のとき、鳥取の士族である前田為二を婿養子として迎え、結婚しました。しかし、為二は貧しさに耐えられず、わずか1年で家を出てしまいます。経済的な困窮と将来への不安から、為二は逃げるように去ってしまったのです。セツは再び一人となり、生活のために様々な仕事に就きました。
1890年、明治23年、英語教師として松江にやってきたラフカディオ・ハーンの住み込みの手伝いとして働くようになります。セツは日本の文化や風習、言葉をハーンに教える役割を果たし、二人は次第に心を通わせるようになりました。興味深いことに、セツが八雲に最初に語った物語が、前夫・前田為二との出会いや別れのきっかけとなったエピソードだったといわれています。八雲はセツの人生の物語に深く興味を持ち、セツの語りの才能を見出しました。
セツは夫ハーンに、日本各地の民話や怪談、伝説を語って聞かせました。ハーンは日本語の読み書きができなかったため、セツの語りが彼の創作活動の源泉となりました。セツは単に物語を伝えるだけでなく、その背景にある文化や心情を丁寧に説明したといわれています。養母トミから受け継いだ語りの技術と、幼い頃から聞いてきた出雲の神話や伝説の数々が、セツの語りを豊かなものにしました。
セツは学校教育を十分に受けることができませんでした。そのことをセツ自身は恥じており、「私には学歴がない」と語ったことがあります。しかし、ハーンはそんなセツに対して、セツが持っていた豊かな口承文化の知識、語りの才能、そして深い人間性こそが、八雲の作品を支える柱となったことを認めていました。学歴という形式的なものよりも、セツの持つ本質的な知識と感性が、世界に誇る文学を生み出す力となったのです。
ぐるっと松江堀川めぐりの魅力
松江市内では堀川めぐりが大変人気です。「ぐるっと松江堀川めぐり」は、国宝松江城のお堀をめぐる遊覧船で、城下町の風景と四季を楽しむことができます。所要時間は約50分で、17の橋をくぐりながら進みます。
橋の中には非常に低いものもあり、船の屋根を下げて通過する場面もあります。この体験が観光客に大変好評で、スリルと楽しさを味わえます。船頭さんの案内も楽しく、松江の歴史や文化について学びながら遊覧することができます。船頭さんは地元の方が多く、松江愛に溢れたガイドが心に残ります。
料金は大人1600円、中高生1300円、小学生800円となっています。運航時間は3月から9月までが9時から17時、10月から2月までが9時から16時です。11月から4月までは、全ての船が「こたつ船」として運航されます。暖かいこたつに入りながら冬の城下町の風景を楽しむことができ、寒い季節でも快適に堀川めぐりを楽しめます。こたつに入りながらの遊覧は、他ではなかなか体験できない特別なひとときです。
事前予約制の「お茶船」も人気です。料金は1人2000円で、船上で抹茶と松江の和菓子を楽しみながら遊覧することができます。お茶と和菓子を味わいながら、ゆったりとした時間を過ごすことができる特別な体験です。松江の和菓子文化を堀川めぐりと合わせて楽しめる、贅沢な時間となっています。
乗船場付近には、松江堀川ビアホールなどの施設もあり、老舗和菓子店の銘菓も販売されています。堀川めぐりの前後に立ち寄って、松江の食文化を楽しむこともできます。
松江の和菓子文化と茶の湯
松江は和菓子の街としても知られており、お茶と和菓子を楽しむ文化が深く根付いています。松江藩主の松平不昧公が茶の湯を愛好したことから、松江には茶の湯文化が花開き、それに伴って和菓子文化も発展しました。不昧公は茶人としても有名で、その影響が今も松江の文化に色濃く残っています。
市内には多くの老舗和菓子店があり、伝統的な製法で作られた銘菓が楽しめます。観光の合間に和菓子店を訪れ、お茶と和菓子をいただくのは、松江観光の醍醐味の一つです。店内でゆっくりとお茶をいただきながら、松江の歴史や文化に思いを馳せる時間は、心を豊かにしてくれます。
風流堂の「堀川めぐり」という名前の和菓子もあります。柔らかい求肥に北海道産の小豆餡を包み、焼き皮で包んだもので、堀川遊覧の思い出として人気のお土産となっています。このように、松江の観光名所にちなんだ和菓子も多く、食べることで松江の思い出を持ち帰ることができます。
松江の和菓子文化は、単なる菓子作りにとどまらず、茶道や日本文化全体と深く結びついています。和菓子を通じて、松江の歴史と文化を感じることができます。和菓子の美しい見た目や繊細な味わいは、日本の美意識を体現しています。
松江と出雲を巡る旅の楽しみ方
松江市と隣接する出雲市は、合わせて観光することで、より充実した島根観光を楽しむことができます。松江と出雲は一畑電車、通称「ばたでん」で結ばれており、公共交通機関でも移動が可能です。
一畑電車は、松江しんじ湖温泉駅から出雲大社前駅までを結ぶ鉄道で、宍道湖の北岸を走ります。車窓からは美しい湖の景色を眺めることができ、移動自体が観光の一部となります。ローカル線ならではのゆったりとした時間の流れを楽しむことができます。
出雲大社は、縁結びの神様として知られる大国主大神を祀る神社で、日本を代表するパワースポットです。本殿の背後には八雲山があり、素鵞社の奥には八雲山の岩肌が露出しています。この場所は強力なパワースポットとして知られており、多くの参拝者が訪れます。
興味深いことに、「八雲」という名前は、出雲の地に深く関わりがあります。素戔嗚尊が詠んだとされる日本最古の和歌「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」が出雲の地と結びついており、「八雲」は出雲を象徴する言葉でもあります。小泉八雲というペンネームを選んだことにも、この地との深い縁を感じることができます。
1泊2日や2泊3日で松江と出雲を巡る観光プランも人気です。出雲大社での縁結び祈願、玉造温泉での湯治、松江での小泉八雲ゆかりの地巡りなど、様々な魅力を組み合わせることができます。温泉で旅の疲れを癒しながら、島根の豊かな自然と文化を満喫する旅は、心身ともにリフレッシュできる素晴らしい体験となります。
松江観光のおすすめプラン
「ばけばけ」のロケ地を巡る松江観光は、ドラマファンだけでなく、歴史や文化に興味のある方にもおすすめです。小泉八雲記念館と旧居は、セットで見学することで八雲の世界をより深く理解することができます。記念館では八雲の生涯と作品について学び、旧居では実際に八雲とセツが暮らした空間を体感できます。二つの施設は隣接しているため、効率よく見学することができます。
八重垣神社は縁結びのパワースポットとして人気があり、鏡の池での恋占いは多くの観光客が体験しています。神社の境内は静かで神聖な雰囲気があり、心が洗われるような感覚を味わえます。ドラマのロケ地としても注目されており、トキが恋占いをしたシーンを思い出しながら訪れると、より感慨深いものがあります。
松江城は国宝天守を有する名城で、天守からの眺めは絶景です。城下町の風情が残る周辺の街並みも見どころで、歴史散策を楽しむことができます。特に塩見縄手は江戸時代の面影を色濃く残しており、ゆっくりと散策することをおすすめします。
宍道湖の夕日は必見です。湖畔には夕日スポットが整備されており、美しい夕景を眺めながらゆったりとした時間を過ごすことができます。夕暮れ時に湖畔を訪れ、オレンジ色に染まる空と湖面を眺める時間は、松江観光のハイライトとなるでしょう。
堀川めぐりも外せません。約50分の遊覧で、松江城のお堀をめぐりながら城下町の風景を楽しむことができます。船頭さんの案内を聞きながら、水上からの視点で松江の魅力を発見できます。冬季はこたつ船、事前予約でお茶船も楽しめます。
和菓子店巡りもおすすめです。松江には多くの老舗和菓子店があり、それぞれが伝統の味を守り続けています。お店で和菓子とお茶をいただきながら、松江の和菓子文化に触れることができます。お土産として購入すれば、旅の思い出を自宅でも味わうことができます。
1日で主要なスポットを巡ることも可能ですが、ゆっくりと松江の雰囲気を味わうなら1泊2日がおすすめです。松江しんじ湖温泉に宿泊すれば、温泉を楽しみながら、宍道湖の朝日や夕日を眺めることができます。朝の静かな宍道湖も美しく、早起きして湖畔を散歩するのも心地よい体験です。
ドラマ「ばけばけ」が伝えるメッセージ
「ばけばけ」は、単なる夫婦の物語ではなく、明治という激動の時代を生きた女性の物語でもあります。武家社会の崩壊、身分制度の変化、西洋文化の流入といった時代の波の中で、トキがどのように生き抜いたかが描かれています。
国際結婚という当時としては極めて稀な選択をしたトキの勇気、そして語り部として夫の創作活動を支えた姿は、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。困難な状況の中でも、自分の才能を活かし、夫と協力して文学作品を生み出していく姿は、現代の女性にとっても励みとなる物語です。
ドラマのオープニング映像は、松江の美しい風景が印象的に使用されており、視聴者から「松江って素敵な街ですね」という声が多く寄せられています。宍道湖の夕日、松江城の風情、堀川の水辺など、松江の魅力がたっぷりと詰まった映像となっています。
主演の髙石あかりさんは、一般公募から選ばれた新人女優で、初々しさと芯の強さを併せ持つトキを熱演しています。ヘブン役のトミー・バストウさんも、日本文化に深い関心を持つ外国人教師を説得力を持って演じています。二人の自然な演技が、ドラマに深い説得力を与えています。
ドラマでは、トキとヘブンの出会いから結婚、そして共に作品を作り上げていく過程が丁寧に描かれています。二人の絆、家族の愛、そして芸術への情熱が、物語の中心となっています。文化や言葉の違いを乗り越え、互いを尊重し合いながら生きる二人の姿は、現代の国際化社会においても重要なメッセージを伝えています。
ドラマを通じて、明治という時代、国際交流の黎明期、そして文学の力を感じることができます。松江の美しい風景とともに、小泉八雲とセツの物語は、これからも多くの人々の心に残り続けることでしょう。「ばけばけ」が教えてくれるのは、困難な時代を生き抜いた女性の強さと、文化や言葉の壁を超えた真の愛の物語です。
セツは学歴がないことを恥じていましたが、彼女が持っていた豊かな知識と語りの才能こそが、世界に誇る文学作品を生み出す原動力となりました。形式的な学歴よりも、本質的な知識と感性の方が重要であることを、セツの人生が教えてくれます。
松江市が持つ怪談のふるさととしての魅力
松江市は、「怪談のふるさと」として知られており、八雲が収集した怪談の多くが松江やその周辺地域を舞台としています。月照寺、松江城、八重垣神社など、八雲が訪れた場所は今でも多くの観光客が訪れる名所となっています。
八雲は松江滞在中に、地元の人々から様々な怪談や伝説を聞きました。特に妻のセツから聞いた物語が、八雲の創作活動の大きな源泉となりました。セツは養母トミから受け継いだ出雲の神話や伝説を、豊かな表現力で八雲に語って聞かせました。
松江の街には、今も怪談や伝説にまつわるスポットが点在しています。月照寺の大亀の伝説、松江城の天守に伝わる話など、松江を訪れることで、八雲の作品の舞台を実際に体験することができます。夜の松江城周辺を歩くと、怪談の舞台にふさわしい幻想的な雰囲気を感じることができます。
八雲の怪談は、単に恐怖を煽るだけのものではありません。日本の美意識、死生観、自然への畏敬の念が込められており、深い文学性を持っています。松江を訪れることで、これらの作品がどのような土地から生まれたのかを理解することができます。
松江市内には小泉八雲記念館のほか、小泉八雲旧居、松江歴史館など、八雲ゆかりの施設が点在しています。これらの施設をめぐることで、八雲とセツが歩んだ道のりをたどることができます。各施設では、八雲の生涯や作品について学ぶことができ、松江という土地が八雲に与えた影響を深く理解することができます。
水の都・松江の魅力
松江市は水の都としても知られ、宍道湖や堀川など、水辺の風景が美しい街です。八雲もこの風景を愛し、作品の中で松江の美しさを讃えています。「神々の国の首都」と表現した松江への愛情は、八雲の作品の随所に感じることができます。
宍道湖は、松江市と出雲市にまたがる日本で7番目に大きい湖です。汽水湖であるため、シジミをはじめとする豊富な水産資源に恵まれています。宍道湖のシジミは「宍道湖七珍」の一つとして知られ、松江の食文化を支えています。
堀川は松江城を囲む水路で、江戸時代には物資の輸送路として重要な役割を果たしていました。現在では観光遊覧船が運航されており、水上から城下町の風景を楽しむことができます。堀川沿いには柳並木が続き、四季折々の美しい風景を見せてくれます。
水辺の風景は、松江の穏やかで落ち着いた雰囲気を作り出しています。八雲とセツも、この水辺を散策しながら、様々な物語について語り合ったことでしょう。水面に映る空や樹木、静かに流れる水の音は、心を落ち着かせてくれます。
朝ドラ「ばけばけ」の放送により、松江市は再び注目を集めています。ドラマのロケ地を巡る観光ツアーも企画されており、多くの観光客が訪れています。松江市を訪れる観光客の数は、ドラマの放送開始以降、大きく増加しており、聖地巡礼の地として定着しつつあります。
松江市は、歴史、文化、自然、食など、様々な魅力を持つ街です。小泉八雲とセツの物語を通じて、この街の奥深い魅力を発見することができます。ドラマ「ばけばけ」を見て興味を持った方は、ぜひ実際に松江を訪れて、その魅力を体感してください。八雲とセツが愛した松江の風景は、今も変わらず訪れる人々を迎えてくれます。
まとめ:松江市で体験する「ばけばけ」の世界
朝ドラ「ばけばけ」は、小泉八雲の妻セツをモデルとした物語で、松江市を主な舞台としています。小泉八雲記念館や旧居、八重垣神社、松江城、宍道湖など、松江市内の多くのスポットがロケ地として使用され、ドラマの世界観を形作っています。これらのロケ地を実際に訪れることで、ドラマの感動を追体験することができます。
小泉八雲とセツの物語は、国際結婚という困難を乗り越え、互いを尊重し合いながら文学作品を生み出していった夫婦の愛の物語です。セツの語りが八雲の『怪談』をはじめとする作品の源泉となり、二人の協働が世界に誇る文学を生み出しました。この物語は、困難な時代を生き抜いた女性の強さと、真の愛の力を教えてくれます。
セツは、生後7日で養子に出され、11歳から働き始め、最初の結婚では夫に去られるという苦難の人生を歩みました。しかし、養母トミから受け継いだ語りの才能と、出雲の神話や伝説の豊かな知識が、八雲の文学作品を支える柱となりました。セツの存在なくして、八雲の偉大な作品は生まれなかったといえます。
松江市は、八雲とセツゆかりの地として多くの史跡や施設が保存されており、ドラマのロケ地を巡りながら二人の足跡をたどることができます。「ばけばけ」の放送により、松江市は聖地巡礼の地として再び脚光を浴びており、多くの観光客が訪れています。ドラマを見て松江に興味を持った方は、ぜひ実際に訪れてみてください。
松江城、堀川めぐり、宍道湖の夕日、和菓子文化、そして小泉八雲ゆかりの地。松江には様々な魅力が詰まっています。隣接する出雲市と合わせて訪れることで、さらに充実した島根観光を楽しむことができます。出雲大社での縁結び祈願と合わせて、松江での小泉八雲ゆかりの地巡りを楽しむプランは、特におすすめです。
ドラマを通じて、明治という時代、国際交流の黎明期、そして文学の力を感じることができます。松江の美しい風景とともに、小泉八雲とセツの物語は、これからも多くの人々の心に残り続けることでしょう。「ばけばけ」が教えてくれるのは、困難な時代を生き抜いた女性の強さと、文化や言葉の壁を超えた真の愛の物語です。
松江市を訪れることで、ドラマの世界を体験するだけでなく、日本の歴史や文化、そして人間の普遍的な愛の物語に触れることができます。小泉八雲記念館でじっくりと展示を見学し、旧居で八雲とセツが過ごした空間を体感し、宍道湖の夕日を眺めながら二人の物語に思いを馳せる。そんな贅沢な時間を、ぜひ松江で過ごしてください。


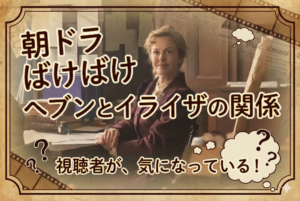
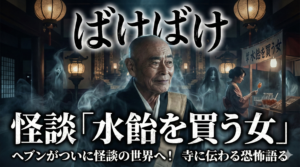


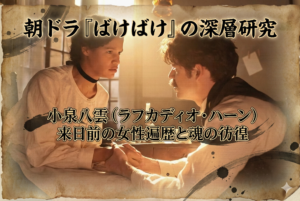

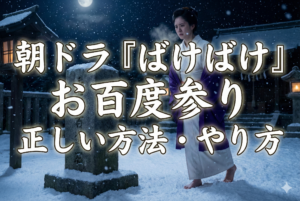

コメント