2025年9月29日から放送が開始されるNHK連続テレビ小説第113作『ばけばけ』は、小泉八雲とその妻セツをモデルにした物語です。激動の明治時代を舞台に、怪談を愛する松野トキと外国人英語教師レフカダ・ヘブンが出会い、文化の違いや偏見を乗り越えて心を通わせていく姿が描かれます。このドラマの精神を象徴するキャッチコピー「この世はうらめしい、けど、すばらしい。」という言葉は、まさに松江という土地そのものを表現しています。松江は小泉八雲が愛した城下町であり、怪談のふるさととして知られる歴史と伝説が息づく場所です。松江のロケ地巡りは、単なる撮影スポットを訪れるだけでなく、八雲とセツが実際に生活し、愛した風景の中に物語の真髄を見出す旅となります。朝ドラ『ばけばけ』のファンにとって、松江は聖地そのものであり、ドラマの世界観を五感で体験できる特別な場所なのです。

小泉八雲が愛した塩見縄手を歩く
松江のロケ地巡りで最初に訪れたいのが、塩見縄手です。この通りは松江城の北堀沿いに続く武家屋敷の通りで、『日本の道100選』にも選ばれています。松江市の伝統美観保存区域に指定されており、江戸時代から続く城下町の風情が色濃く残されています。通りの名前は、松江藩の中老である塩見小兵衛に由来するとも、細くまっすぐな一本道を意味する縄手から来ているとも言われています。堀沿いに並ぶ老松の影が水面に落ち、その景観はまるで時が止まったかのような美しさです。
小泉八雲は1890年に来日し、その5ヶ月後に松江の尋常中学校の英語教師として赴任しました。松江での滞在期間はわずか1年3ヶ月でしたが、この地での経験が彼の作家人生を決定づけたのです。八雲は「へるん先生」として地元の人々に親しまれ、毎日のようにこの堀端を散歩していました。朝ドラ『ばけばけ』でも、明治の空気と武士の時代の残り香が混じり合うこの風景が重要な舞台となるでしょう。塩見縄手を歩けば、ドラマの主人公たちが感じた松江の空気感を肌で感じることができます。
小泉八雲旧居で日本の美に触れる
塩見縄手の中ほどに位置する小泉八雲旧居は、松江のロケ地巡りにおいて最も重要な場所です。ここは八雲がセツと新婚生活を送った武家屋敷で、当時のままの姿で保存されています。八雲は西洋の家具を置かず、着物で過ごし、日本人のように暮らすことを選びました。この旧居で彼が何よりも愛したのが、縁側から見える小さな枯山水の庭園です。
八雲は一日中この庭を眺めて過ごしたと伝えられています。縁側に腰掛けて静かに時を過ごせば、鳥の声や草木の香り、風の音が五感を刺激します。「言葉の画家(ワード・ペインター)」と呼ばれた八雲が、この庭から感じ取った日本の美の片鱗に触れることができるでしょう。朝ドラ『ばけばけ』のヒロイン・トキとヘブンが心を通わせていく場面のモデルとなったのも、まさにこの場所なのです。
旧居のすぐ隣には小泉八雲記念館が併設されています。ここでは、作家でありジャーナリストでもあった八雲の生涯と、その豊かな文学世界に触れることができます。展示の中でも特に注目すべきは、八雲が愛用した遺品の数々です。直筆の原稿や初版本はもちろん、特注の机と椅子は見る者を感動させます。八雲は視力が非常に弱かったため、顔を紙に近づけて執筆できるよう、天板が高く傾斜した特別な机を使用していました。『怪談』や『知られぬ日本の面影』といった不朽の名作が、この机から生み出されたと思うと、深い感慨が湧いてきます。
島根県尋常中学校跡と山口薬局の物語
塩見縄手の周辺には、八雲の日常を感じられるスポットがさらにあります。島根県尋常中学校跡の碑は、八雲が「へるん先生」として教鞭をとった場所を示しています。生徒たちから深く慕われていた八雲の人柄が、この場所から伝わってきます。
そして、朝ドラ『ばけばけ』のファンにとって非常に重要なのが、現在も営業を続けている山口薬局です。脚本家のふじきみつ彦さんは、松江への取材でこの薬局を訪れた際、「当時、松江でビールを売っていたのはここだけだった」という逸話に感銘を受けました。この逸話がドラマのエピソードの着想源になったと語っています。西洋化が進む明治の松江で、外国人教師ヘブンが唯一ビールが手に入る薬局を訪れる姿を想像するだけで、ドラマのワンシーンが目に浮かびます。この薬局は、物語と現実が交差する聖地そのものなのです。
怪談のふるさと松江を巡る
朝ドラ『ばけばけ』のヒロイン・松野トキは、怪談話が好きな少し変わった女性として描かれます。そのモデルであるセツは、毎晩のように松江の古い伝承や怪談を八雲に語り聞かせました。八雲はそれらを熱心に聞き取り、世界的な文学作品へと昇華させたのです。松江は「怪談のふるさと」と呼ばれるほど、今もなお多くの伝説が息づいています。
小豆とぎ橋の伝説は、松江の代表的な怪談スポットです。この橋の近くにある普門院の付近には、かつて橋があり、夜な夜な女の幽霊が現れては橋の下で小豆を洗う音がしたと言われています。さらに奇妙なタブーとして、謡曲『杜若(かきつばた)』を謡いながら歩くと、必ず良くないことが起きるという言い伝えがありました。なぜ『杜若』なのかは定かではありませんが、そうした理屈を超えた畏れこそが怪談の本質を表しています。
松江の怪談は、寺社にも数多く残されています。月照寺の大亀の伝説は特に有名です。松江藩主・松平家の菩提寺である月照寺にある巨大な石亀が、夜な夜な町に出て人を襲ったという物語が伝えられています。また、八雲自身が感銘を受けたのが龍昌寺の微笑する地蔵です。八雲は寺町通りにあるこの寺で、名工・荒川亀斎が彫った地蔵を見つけ、「夢見るごとき観音や微笑している地蔵を見つけることができる」と記しました。残念ながらその地蔵は罹災で失われましたが、復元されたものが現在、小泉八雲記念館に展示されています。
松江ゴーストツアーで怪談を体験する
これらの怪談スポットを昼間に訪れるだけでは物足りないと感じる方には、松江ゴーストツアーへの参加をおすすめします。これは地元の語り部(ストーリーテラー)の案内で、夜の暗闇の中、松江の怪談ゆかりの地を巡るツアーです。単なるお化け屋敷とは全く異なり、暗闇の中で五感を研ぎ澄まし、プロの語り部が紡ぐ物語に耳を傾ける本格的な体験となります。
このツアーは、八雲がセツから怪談を聞いた夜の「うらめしさ」と「すばらしさ」を、最も色濃く追体験できる時間です。朝ドラ『ばけばけ』のキャッチコピー「この世はうらめしい、けど、すばらしい。」という言葉の意味を、身をもって理解することができるでしょう。松江ゴーストツアーは松江観光協会によって商標登録もされており(登録番号 第5262591号)、松江が誇る本格的な文化体験として高く評価されています。
国宝松江城から水の都を一望する
松江のロケ地巡りでは、国宝松江城も外せません。松江のシンボルであるこの城は、現存する12天守の一つであり、その堂々たる姿は圧巻です。八雲も松江城の周りを散歩するのが日課で、特に城山稲荷神社にいる狐の石像をよく眺めていたと伝えられています。
天守閣に登れば、松江市街はもちろん、八雲が愛した宍道湖の雄大な景色まで一望できます。朝ドラ『ばけばけ』の舞台となる町全体を、ヘブン(八雲)と同じ視点から見下ろすことができるのです。城下町の美しい街並みと、水の都と呼ばれる松江の全景を眺めることで、なぜ八雲がこの地を愛したのかが深く理解できます。
ぐるっと松江堀川めぐりで水上散歩
松江城を外から楽しむ最高の方法が、ぐるっと松江堀川めぐりです。松江城の堀を小舟で巡るこの遊覧船は、日本でここだけの体験と言われています。乗船場は3箇所あり、松江城のふもと「大手前乗船場」や、小泉八雲記念館の近く「ふれあい広場乗船場」から乗ることができます。
コースは約50分で一周します。武家屋敷が並ぶ歴史区、緑豊かな自然区、そして現在の町並みが続く市街地区と、松江の多様な顔を水の上から眺めることができます。この遊覧船のハイライトは、低い橋の下をくぐる瞬間に船の屋根が自動で下がることです。乗客全員が頭を下げてスリルを味わう、ユニークなアトラクションでもあります。
堀川めぐりの乗船券は、当日中何度でも乗降可能という大きな利点があります。これは単なる50分の観光アトラクションではなく、松江の主要観光地を結ぶ水のタクシーとして利用できることを意味します。例えば、松江城の「大手前乗船場」から乗船し、水の上から城下町の風景を楽しみながら、塩見縄手の最寄りである「ふれあい広場乗船場」で下船します。小泉八雲旧居や記念館をじっくり観光した後、再び「ふれあい広場乗船場」から乗船して残りのコースを楽しむことができるのです。このように堀川めぐりを移動手段として組み込むことで、旅の効率が格段に上がり、何よりもロマンチックな水の都の体験が深まります。
不昧公三大銘菓で松江の甘味を堪能
松江のロケ地巡りの合間には、この町が持つ美味しい文化も体験しましょう。松江は、京都や金沢と並び称される日本三大和菓子処の一つです。その背景には、江戸時代の松江藩七代藩主・松平治郷(まつだいら はるさと)の存在があります。彼は「不昧(ふまい)」という茶号を持つ大名茶人であり、松江に茶の湯文化を深く根付かせました。
不昧公が愛したとされる不昧公三大銘菓は、松江のロケ地巡りのお土産として最適です。一つ目は、彩雲堂の「若草」です。ふっくらとした求肥に、鮮やかな緑色の寒梅粉をまぶしたお菓子で、その名の通り春の新芽のような瑞々しさが特徴です。二つ目は、風流堂の「山川」で、赤と白の対比が美しい落雁です。口に入れるとさっと溶けて上品な甘さが広がり、日本三大銘菓の一つにも数えられる逸品です。三つ目は、三英堂の「菜種の里」で、黄色い落雁の中に煎り米が入っており、春の菜の花畑を蝶が舞う情景を表しています。
これら老舗の本店は、JR松江駅から徒歩圏内に集まっています。旅の始まりや終わりに、まとめて訪れることができるのも大きな魅力です。八雲もセツも、こうした和菓子を味わいながら、松江の文化に触れていたことでしょう。
神代そばで出雲の伝統を味わう
松江のロケ地巡りでの昼食には、出雲そばがおすすめです。黒っぽい麺と濃いめのつゆが特徴の出雲そばは、八雲も愛したであろう、この地のソウルフードです。数ある名店の中でも、堀川めぐりの「ふれあい広場乗船場」から徒歩わずか4分という絶好のロケーションにあるのが神代そばです。
ここは食べログ百名店2025にも選ばれた実力派で、地元産と他の産地の蕎麦をブレンドし、すべて生粉打ち(十割)で提供するのがこだわりです。硬めでコシのある麺を、やや辛めのつゆに少しだけつけて噛みしめると、蕎麦本来の旨みが口いっぱいに広がります。小泉八雲旧居や記念館を訪れる前後に立ち寄れば、効率的に松江の味を楽しむことができます。
地酒と名物おつまみで松江の夜を満喫
朝ドラ『ばけばけ』のロケ地巡りで充実した一日を過ごした後は、松江の美味しい地酒で乾杯しましょう。もし一軒だけ専門的な店を選ぶとしたら、七三(しちさん)がおすすめです。ここは島根県の地酒のほとんどの銘柄が揃うという居酒屋で、店主が日本酒のソムリエである「きき酒師」の上位資格である「酒匠(さかしょう)」の持ち主です。日本酒の知識がなくても、好みを伝えれば最適な一本を選んでもらえます。
この店でぜひ試してほしいのが、名物「にんじんの一本揚げ」です。出汁で蒸したニンジンを丸ごと揚げたという驚きのアイデアおつまみで、地酒との相性も抜群です。松江の夜を「すばらしい」ものに変えてくれる、特別な一品です。
松江へのアクセスと市内交通
松江へのアクセスは、東京からは飛行機が便利ですが、大阪や京都、広島といった近隣の大都市からは、JRの高速バスが非常に便利です。例えば、大阪駅のJR高速バスターミナルから出発する「グラン昼特急出雲号」に乗れば、約4時間半で松江駅に到着します。京都駅烏丸口からも便が出ています。旅費を節約したい、あるいは時間を有効に使いたい場合は、夜行バスも選択肢になります。大阪駅JR高速バスターミナルを夜に出発すれば、翌朝の早朝には松江駅に到着し、朝一番から活動を開始できます。
松江駅に到着したら、次に入手すべきは市内の足です。松江市内の主要な観光スポットは、レトロな外観が可愛らしい周遊バスぐるっと松江レイクラインがほぼ全て網羅しています。このバスは、1回の乗車運賃が大人210円、小人110円です。しかし、ロケ地巡りで3箇所以上を巡るなら、絶対にレイクライン1日乗車券がおすすめです。
価格はなんと、大人520円、小人260円です。わずか520円で、この便利なバスが1日中乗り放題になります。この紙の乗車券は、JR松江駅構内にある『おみやげ楽市シャミネ松江店』や、松江しんじ湖温泉駅の売店で購入可能です。また、JR西日本の観光ナビアプリ『tabiwa by WESTER』を使えば、デジタルチケットとしても購入できます。
朝ドラばけばけファンのためのばけバス
もし自身のプランニングに自信がない、あるいは「とにかく『ばけばけ』関連の場所に絞って効率よく巡りたい」という方には、期間限定で運行される可能性のある周遊観光バスばけバスという選択肢も出てくるかもしれません。これは小泉八雲とセツの思い出の地を約3時間半でお手軽に巡ることができるツアーバスです。堀川めぐりや地酒を楽しむ自由度はありませんが、短時間で聖地のハイライトを押さえたい方には最適です。
松江ロケ地巡りのモデルコース
朝ドラ『ばけばけ』のロケ地を効率よく巡るための、完璧な1日をご提案します。朝、松江駅に到着したら、まず『おみやげ楽市』で「レイクライン1日乗車券」(520円)を購入します。レイクラインバスに乗り、「堀川遊覧船ふれあい広場乗船場」で下車します。乗船場から徒歩4分の「神代そば」で、少し早めの昼食をとります。
腹ごしらえをしたら、「ふれあい広場乗船場」から堀川めぐりの舟に乗り込みます。水上から塩見縄手の武家屋敷を眺め、そのまま舟で松江城の「大手前乗船場」へ向かいます。松江城天守閣に登り、松江の町を一望します。再びレイクラインバスに乗り、今度は「小泉八雲記念館前」で下車します。
午後をたっぷり使い、小泉八雲旧居で庭を眺め、記念館で八雲の生涯に触れ、塩見縄手を散策し、山口薬局でドラマの空気を感じます。もし時間が許せば、月照寺や小豆とぎ橋の伝説の地まで足を延ばしてみましょう。そして夕刻、旅のクライマックスである宍道湖の夕日へと向かいます。
宍道湖の夕日で感動のフィナーレ
朝ドラ『ばけばけ』の聖地巡礼、その長い1日の終わりは、八雲が愛し、彼の作品にも大きな影響を与えた宍道湖の夕日で締めくくるべきです。このドラマのテーマ「この世はうらめしい、けど、すばらしい。」という言葉が、この夕日の中に凝縮されています。塩見縄手の歴史、武家屋敷の没落、セツが語った怪談の世界に「うらめしさ」を感じた1日だったかもしれません。しかし、その全てを包み込み、肯定するような圧倒的な「すばらしさ」が、この宍道湖の夕日にはあります。
この夕日を鑑賞するために、松江には夕日指数という予報があるほどです。鑑賞スポットはいくつかありますが、最もドラマチックな体験ができるのは島根県立美術館です。「夕日につつまれる美術館」というコンセプトの通り、宍道湖に面したロビーは全面ガラス張りです。しかもこのエントランスロビーは入場無料で、湖に向かってソファが並べられています。まるで夕日そのものを鑑賞するために設計された神殿のようです。
日没の時間が近づくと、空と湖は燃えるようなオレンジ色から、息をのむような紫、そして深い藍色へと刻一刻と変化していきます。まさに「化けていく」という表現がぴったりです。写真にこだわるなら、湖畔に整備された宍道湖夕日スポット とるぱがおすすめです。ここは「夕日を撮るパーキング」の略で、宍道湖の象徴である「嫁ケ島(よめがしま)」をシルエットにして撮影できる絶好のポイントです。
また、松江の町と夕日を一緒に楽しみたいなら、宍道湖大橋の上も良いでしょう。橋の中ほどにはベンチが置かれたスペースもあり、散歩しながら夕景を楽しめます。宍道湖に沈む夕日を眺めながら、私たちは八雲が、そして朝ドラ『ばけばけ』のトキとヘブンが感じたであろう感動を追体験します。「うらめしい」ことの多いこの世界も、見方を変えれば、こんなにも「すばらしい」瞬間に満ちているのです。
松江が伝える八雲とセツの物語
小泉八雲は松江の地で、失われつつあった日本の面影を見出しました。彼は怪談という「うらめしい」物語の中にさえ、人間の真実やかけがえのない美しさがあることを見抜いたのです。朝ドラ『ばけばけ』は、その八雲とセツの精神を現代に蘇らせる物語です。松江のロケ地巡りは、ドラマを見る前の予習としても、放送開始後の聖地巡礼としても、最高の体験となります。
松江という町は、単なる観光地ではありません。ここは八雲とセツが愛し、生活し、物語を紡いだ場所です。朝ドラ『ばけばけ』の聖地として、松江はその真実を全身で感じさせてくれる特別な場所なのです。2025年9月29日から始まる朝ドラ『ばけばけ』の放送に向けて、この歴史と伝説が息づく町へ、ぜひ旅に出かけてみてください。松江のロケ地巡りは、あなたの人生を「すばらしい」ものへと「化けて」いく、忘れられない体験となることでしょう。




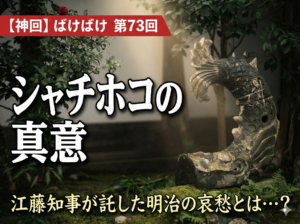


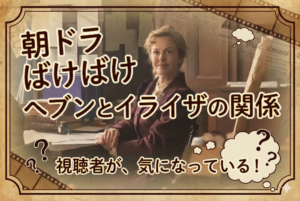
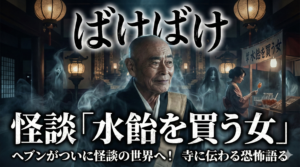

コメント