2025年秋からNHKで放送されている連続テレビ小説「ばけばけ」において、視聴者の注目を集めているキャラクターの一人が江藤リヨです。北香那さんが演じるこの役は、島根県知事の娘として登場し、英語が堪能で才色兼備、積極的な性格でヒロインの恋路を揺さぶる存在として描かれています。「江藤リヨには実在のモデルがいるのか」「もしいるなら誰なのか」という疑問を持つ方は多いでしょう。結論から申し上げると、江藤リヨのモデルとなった人物は実在しており、当時の島根県知事であった籠手田安定(こてだ やすさだ)の娘がそのモデルとされています。ただし、ドラマで描かれる積極的で恋のライバルとしての姿は脚色であり、史実における彼女は静謐で上品な女性として伝えられています。本記事では、江藤リヨのモデルとなった実在の人物について詳しく解説するとともに、ドラマ「ばけばけ」の歴史的背景や、ヒロインのモデルである小泉セツとの関係性についても深く掘り下げていきます。

朝ドラ「ばけばけ」とは何か
連続テレビ小説「ばけばけ」は、明治時代の松江を舞台に、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・小泉セツをモデルとした物語です。ドラマでは、ヒロインの松野トキが小泉セツに相当し、異国からやってきた作家との出会いから始まる人生を描いています。タイトルの「ばけばけ」は、小泉八雲が収集した怪談や日本の妖怪文化を象徴するものであり、急速な西洋化が進む明治期において失われゆく「日本の面影」を記録しようとした外国人作家の姿と、それを支えた日本人妻の物語が展開されます。
「ばけばけ」の放映に伴い、多くの視聴者がドラマに登場する人物のモデルについて関心を寄せています。特に江藤リヨというキャラクターは、没落士族の娘であるヒロインとは対照的に、上流階級の出身として西洋文明と対等に渡り合う「文明開化」の象徴として配置されており、その存在感から実在のモデルがいるのかどうかが話題となっています。
江藤リヨのモデルは実在する
江藤リヨのモデルとなったのは、実在の人物である籠手田安定の娘です。籠手田安定は1840年に生まれ、1899年に亡くなった明治時代の政治家であり、当時の第7代島根県知事を務めていました。ドラマでは「江藤安宗」という名前で佐野史郎さんが演じていますが、これは籠手田安定をモデルとしたキャラクターです。
籠手田安定の娘については、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の書簡や著作の中で言及されており、ハーンは彼女を「日本で最も愛すべき女性(The Sweetest Lady in Japan)」と表現しています。この表現からも分かるように、史実における籠手田の娘は、ドラマで描かれるような「恋のライバル」「物語を掻き乱すキャラクター」というよりは、上品で気配りのできる日本の貴婦人として認識されていました。
ハーンが友人の西田千太郎に宛てた手紙の中では、「出雲知事の娘、日本で最も愛すべき女性から贈られたウグイス」という記述があり、彼女がハーンに対して深い敬意と思いやりを持っていたことが窺えます。ただし、この関係性は恋愛的なものというよりは、高貴な家柄にふさわしい「慈愛」と「風流」の表現であったと解釈されています。
籠手田安定とはどのような人物だったのか
江藤リヨの父親のモデルである籠手田安定について詳しく見ていきましょう。籠手田安定は、小泉八雲が著した「知られぬ日本の面影(Unfamiliar Japan)」の中でも描写されている人物であり、強烈な個性を持った知事として知られていました。
身体的な特徴として、籠手田は「背が高く、力強い男」と表現されており、剣道の達人でもありました。彼は心形刀流や直心影流という剣術を修めた武人であり、知事公舎の庭で剣術の稽古を行うほど熱心に武道に取り組んでいたとされています。当時の地方行政官としては異例ともいえる武人気質を持った人物だったのです。
思想的には、籠手田は保守主義者として知られていました。ハーンは籠手田を「古き良き日本の本質を守ろうとする熱心な提唱者」と評価しており、明治20年代に鹿鳴館外交に代表される極端な欧化主義が地方にも波及する中で、日本の精神的伝統を重んじる姿勢を崩さなかった人物として描いています。この保守的な姿勢こそが、近代化に失望して日本へ逃避してきたハーンと深く共鳴する要因となりました。
籠手田はハーンに対して単なる外国人教師以上の敬意を払っていました。県庁の知事室にハーンを招き入れ、西洋風の絨毯が敷かれベイウィンドウのある部屋で契約を交わしました。また、出雲で作られた古い漆器などの美術品をハーンに見せ、彼の美的感覚を刺激しました。ハーンにとって籠手田は、行政の長であると同時に、愛する「オールド・ジャパン」の守護者として映っていたのです。
籠手田家の隠された歴史とキリシタン大名の末裔
籠手田家には、一般にはあまり知られていない重層的な歴史的背景があります。それは、籠手田家がキリシタン大名の家臣の末裔であるという事実です。ハーン自身がカトリック的な環境に反発して日本に来たことを考えると、この事実は極めて皮肉かつ象徴的な関係性を示しています。
籠手田家は、戦国時代から江戸初期にかけて肥前国平戸(現在の長崎県平戸市)を治めた松浦氏の重臣でした。16世紀半ば、籠手田安経とその弟である一部勘解由は、イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルらの影響を受けてキリスト教に改宗しました。彼らの領地であった平戸島西岸の根獅子や生月島では、領主の入信に伴って住民の一斉改宗が行われ、1558年と1565年の記録によれば、この地域は日本で最もキリスト教が繁栄した場所の一つとなりました。
しかし、豊臣秀吉によるバテレン追放令、続く徳川幕府の禁教令により状況は一変します。1599年、主君である松浦氏は幕府への忠誠を示すため、籠手田一族に対し信仰を捨てるか領地を去るかを迫りました。籠手田一族は約600名の家臣や領民と共に長崎へと退去する道を選びました。この時、平戸に残された領民たちは、表向きは仏教徒を装いながら密かに信仰を守り続ける「隠れキリシタン(潜伏キリシタン)」となり、「納戸神」と呼ばれる密かな信仰対象を祀り、オラショと呼ばれる祈りを唱え続けました。
明治時代になって、籠手田安定はその末裔として男爵の位を持ち、天皇に仕える官僚となっていました。彼が滋賀県令時代や島根県知事時代に見せた「日本精神の尊重」や「保守的姿勢」の裏には、かつて異国の宗教ゆえに領地を追われた一族の歴史が影を落としていた可能性があります。ハーンは松江で「神々の国の首都」としての日本精神に魅了されましたが、彼を庇護した知事の血脈には、ハーンが忌避した西洋の宗教であるキリスト教の日本における最も劇的な受容と弾圧の歴史が刻まれていたのです。このねじれた関係性は、ドラマでは描かれない深層の歴史ドラマといえるでしょう。
ウグイス贈答事件の真実
江藤リヨのモデルである籠手田知事の娘とハーンの間には、「ウグイス贈答」という有名なエピソードがあります。このエピソードは、ハーンが松江の厳しい冬に直面し体調を崩していた時期、おそらく1891年初頭に発生したとされています。
知事の娘は、異国から来た教師が病床で孤独に過ごしていることを案じ、慰めとしてウグイスを贈りました。これは恋愛的なアプローチというよりは、高貴な家柄にふさわしい「慈愛」と「風流」の表現であったと解釈されています。当時、美しくさえずるように訓練された「飼いウグイス」は極めて高価でした。ハーン自身が手紙の中で述べているように、「1~2円で買えるウグイスもいるが、訓練された籠飼いの歌手は100円を下らないかもしれない」とのことで、当時のハーンの月給(約100~200円程度)に匹敵するような高価な贈り物だったのです。このような贈り物ができるのは、知事家ならではの財力とハーンへの高い評価を示すものでした。
ハーンはこの贈り物を単なるペットとしてではなく、宗教的・文化的なシンボルとして受け取りました。ウグイスの鳴き声「ホーホケキョ」を、ハーンは仏教の経典「法華経(Hokkekyo)」の読経として捉えたのです。ハーンは西田千太郎への手紙の中で、この鳥を「信心深さゆえに、600の眼の功徳、600の耳の功徳、そして舌の1200の超自然的な卓越性を授けられた」「神聖な小鳥」と表現し、自らを「仏教徒」と称するこの鳥に深い愛着を示しました。
知事の娘は、ウグイスという「自然」を贈ったつもりであったかもしれませんが、ハーンはその中に「仏教」「日本の神秘」「宗教的情操」を見出しました。つまり、彼女はハーンに対し、彼が最も求めていた「日本的なるもの」への鍵を手渡したことになります。この点において、彼女は単なる令嬢ではなく、ハーンの霊的探求における重要な存在の一人であったと言えるでしょう。
ドラマのリヨと史実の違い
ドラマ「ばけばけ」における江藤リヨと、史実における籠手田知事の娘には、いくつかの重要な違いがあります。
ドラマでの江藤リヨは、英語が堪能で積極的な性格を持ち、ヒロインの恋路を揺さぶる「ライバルキャラクター」として描かれています。視聴者からは「物語を掻き乱す」「癖が強い」といった印象を持たれることもあるキャラクターです。これに対し、史実における籠手田の娘は、ハーンから「日本で最も愛すべき女性」と称されるほど上品で気配りのできる女性であり、恋愛的なアプローチというよりは文化的な交流を通じてハーンと関わっていました。
また、ドラマでは江藤リヨとヒロインである松野トキの対立構図が描かれていますが、史実においてはそのような対立関係があったという記録は見当たりません。むしろ、籠手田の娘はハーンに対する「文化的後援者(パトロン)」としての側面が強く、日本文化の粋であるウグイスを通じてハーンに日本の美意識を教示した存在でした。
この違いは、ドラマをより面白くするための脚色であると理解するのが適切でしょう。朝ドラでは視聴者を引き込むためにライバルキャラクターを設定することが一般的であり、江藤リヨもそのような役割を担っています。
小泉セツとはどのような人物だったのか
江藤リヨのモデルを理解するためには、ヒロインのモデルである小泉セツについても知っておく必要があります。小泉セツは1868年に生まれ、1932年に亡くなった女性で、ドラマ「ばけばけ」のヒロイン・松野トキのモデルとなっています。
小泉セツは、松江藩の番頭という高い地位にあった小泉湊の娘として生まれましたが、明治維新による秩禄処分と士族の没落により極貧の生活を余儀なくされました。学業成績が優秀であったにもかかわらず、家計を助けるために小学校を中退し、11歳から機織りの仕事に従事しました。
長年の重労働は彼女の身体を変えました。ハーンが初めてセツに会った際、彼は「サムライの娘」を期待していましたが、セツを見て失望したという逸話があります。機織りの労働によって彼女の腕や足は太く逞しくなっており、ハーンは「これはサムライの娘ではない、農家の娘だ」と感じたのです。しかし、ハーンは後にこの認識を改めます。その太い腕こそが、家族のために自己を犠牲にしてきた「孝行」の証であると理解し、そこに道徳的な美しさを見出すようになりました。
セツの苦難は労働だけではありませんでした。18歳で稲垣家の養女として同じく養子の前田為治と結婚しましたが、夫は稲垣家のあまりの貧困に耐えきれず、わずか1年足らずで逃亡してしまいました。離婚して実家に戻ったセツは、世間体を気にしつつも生きるために外国人教師であるハーンの住み込み女中として働く道を選びました。これが運命の出会いとなったのです。
知事の娘とセツの対比
籠手田知事の娘(江藤リヨのモデル)と小泉セツの対比は、ハーンが愛した二つの異なる「日本」を象徴しています。
籠手田の娘は上流階級の出身として、完成された美の象徴でした。高価なウグイスを贈ることができる財力があり、英語や教養を身につけていた可能性が高く、日本の伝統的な美意識や風流を体現する存在でした。ハーンは彼女を「日本で最も愛すべき女性」と称え、その上品さと気配りを高く評価していました。
一方、小泉セツは没落士族の娘として、土着の精神と生存の象徴でした。機織りで太くなった腕は労働の証であり、貧困という現実と闘ってきた人生を物語っていました。彼女はハーンに完成された美を贈ることはできませんでしたが、怪談という「物語の原石」を贈ることができました。
ハーンとセツの間には共通言語がありませんでした。そこで生まれたのが「ハーンさん言葉」と呼ばれる独自のピジン日本語です。「テニヲハ」を抜き、動詞の活用を無視し、名詞を羅列する形式で会話していました。逆説的ですが、流暢な英語で会話ができる相手よりも、不自由な日本語でコミュニケーションをとらざるを得ないセツとの関係が、ハーンの作家としての想像力を刺激しました。セツが語る怪談は、言葉が不完全であるがゆえに身振り手振りや声色を使った「演技」となり、ハーンはその背後にある情念を直感的に掴み取ることができたのです。
ハーンがセツを選んだ理由
なぜハーンは「知事の娘」ではなく「セツ」を選んだのでしょうか。その理由は、単なる恋愛感情を超えた「文学的必然性」にあったと考えられます。
セツはハーンのために、古い本を買い集め、近所の古老から伝説を聞き出し、それをハーンが理解できる簡単な日本語に噛み砕いて語って聞かせました。「耳なし芳一」執筆時には、ハーンが「武士が門を開けさせる時の言葉は『門を開け』で良いか」と尋ねた際、セツは「それでは弱い」とし、より威圧的な「開門!」という言葉を教えました。また、芳一を呼ぶ亡霊の声を演じる際、セツが隣室から「芳一!芳一!」と呼びかけ、ハーンが「はい、私は盲目です」と応じるなど、二人の生活は常に物語の実験場でした。
この「共犯関係」とも言える創作のプロセスは、高貴な知事の娘との間では成立し得なかったでしょう。ハーンが必要としていたのは、西洋的な教養を持つレディではなく、日本の土着的な闇と光を体現し、それを共有してくれるパートナーでした。知事の娘は「完成された美(ウグイス)」を贈りましたが、セツは「物語の原石(怪談)」を贈ったのです。
明治時代の松江という舞台
ドラマ「ばけばけ」の舞台となっている明治時代の松江について理解を深めておくことも重要です。松江はかつて「神々の国の首都」と呼ばれ、出雲大社をはじめとする神話や伝説の宝庫でした。ハーンがこの地に魅了されたのは、西洋化が急速に進む日本において、松江がまだ古い日本の姿を色濃く残していたからです。
1890年にハーンが松江に赴任した当時、日本は明治政府のもとで急速な近代化を進めていました。鹿鳴館に象徴される欧化政策が全国に広がり、伝統的な日本文化は「遅れたもの」として排斥される傾向にありました。しかし松江は、そのような時流からやや離れた場所にあり、古い習俗や伝説が人々の生活の中に息づいていました。
籠手田知事の「保守的姿勢」は、こうした松江の風土を守ろうとする意志の表れでもありました。そしてハーンは、この知事の庇護のもとで、失われゆく「日本の面影」を記録する仕事に取り組むことができたのです。江藤リヨのモデルである知事の娘も、このような文化的背景の中で育った女性でした。
ハーンと猫のエピソード
ハーンとセツの生活には、心温まるエピソードも数多く残されています。その一つが猫にまつわる話です。ハーンとセツは、子供にいじめられていた黒猫を助け、「目が炭火のように赤い」ことから「火の粉(ひのこ)」と名付けて可愛がりました。
また、ハーンは日本の冬の寒さに弱く、学校の火鉢一つでは足りないと不平を言っていたという記録があります。セツはその寒がりな夫のために着物を重ね着させたり、火鉢を世話したりしました。知事の娘からウグイスが贈られたのも、ハーンが風邪で伏せっていた時でした。贈られたウグイスは秋になると鳴かなくなり、ハーンはそれを悲しみ、再び鳴く日を待ち望んだという記述も残されています。
ドラマを楽しむための視点
「ばけばけ」を視聴する際、江藤リヨというキャラクターがどのように史実を基にしつつも脚色されているかを知っておくと、より深くドラマを楽しむことができます。
ドラマにおけるリヨは「恋のライバル」として物語に緊張感をもたらす存在ですが、史実における籠手田の娘は、ハーンに日本文化の粋を教えた「文化的後援者」でした。この違いを理解した上でドラマを見ると、脚本家がどのような意図でキャラクターを造形したのかが見えてきます。
また、ヒロインである松野トキ(小泉セツ)の描かれ方についても、史実と比較しながら見ると興味深い発見があるでしょう。没落士族の娘として貧困と闘いながらも、怪談の語り手としてハーンの創作を支えたセツの姿は、ドラマでどのように表現されているのか注目してみてください。
小泉八雲の文学的遺産
最後に、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の文学的遺産についても触れておきましょう。ハーンは「怪談」「知られぬ日本の面影」「心」などの著作で知られる作家であり、日本の伝統文化や民話を西洋に紹介した功績で高く評価されています。
ハーンが日本で収集し再話した怪談は、「耳なし芳一」「雪女」「むじな」など、現在でも広く知られる物語となっています。これらの作品が生まれた背景には、セツという「共同制作者」の存在がありました。セツが語る怪談を聞き、それを文学作品として昇華させたのがハーンだったのです。
江藤リヨのモデルである籠手田の娘は、ハーンに「完成された美」としてのウグイスを贈りましたが、ハーンの文学を生み出したのは、セツが贈った「物語の原石」でした。この二人の女性の対比は、ハーンが愛した日本の二つの顔を象徴しています。一つは上流階級が守ってきた洗練された文化であり、もう一つは庶民の間で語り継がれてきた土着の物語です。ハーンは後者を選び、それを世界文学の一部として残しました。
まとめ
「ばけばけ」に登場する江藤リヨのモデルは実在しており、当時の島根県知事であった籠手田安定の娘がそのモデルとされています。ただし、ドラマで描かれる積極的な恋のライバルとしての姿は脚色であり、史実における彼女はハーンから「日本で最も愛すべき女性」と称されるほど上品で気配りのできる女性でした。
籠手田家には、キリシタン大名の家臣の末裔という重層的な歴史的背景があり、この事実はハーンとの関係性に皮肉な深みを与えています。また、知事の娘がハーンに贈ったウグイスは、単なるペットではなく、日本文化の粋を象徴する贈り物でした。
一方、ハーンが生涯の伴侶として選んだのは、没落士族の娘である小泉セツでした。彼女は「完成された美」ではなく「物語の原石」を贈ることができる存在であり、ハーンの文学的創作における不可欠なパートナーとなりました。
ドラマ「ばけばけ」を楽しむ際には、このような史実との違いを念頭に置きながら視聴すると、より深い理解と楽しみが得られるでしょう。フィクションとしての江藤リヨが照らし出すのは、史実における小泉セツの輝きであり、ハーンが愛した「日本の面影」の本質なのです。




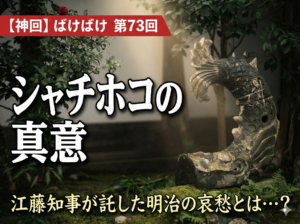


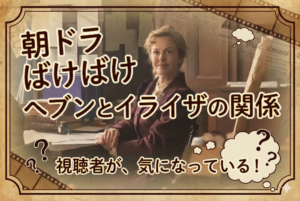
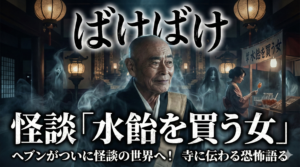

コメント