NHK朝ドラ「ばけばけ」に夏目漱石は登場するのでしょうか。2025年9月29日から放送が開始された連続テレビ小説「ばけばけ」は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻である小泉セツをモデルにした物語です。史実において小泉八雲と夏目漱石には深い因縁があり、漱石は二度にわたって八雲の後任を務めたという歴史的事実があります。そのため、ドラマの後半で東京帝国大学時代が描かれる際に、夏目漱石が登場する可能性は十分に考えられます。しかし、2025年11月25日現在、NHKから夏目漱石役のキャスト発表はされておらず、具体的な登場回も公式には明かされていません。本記事では、「ばけばけ」の作品概要から、小泉八雲と夏目漱石の歴史的な関係性、そしてドラマにおける夏目漱石の登場可能性について詳しく解説していきます。

NHK朝ドラ「ばけばけ」の作品概要
「ばけばけ」は、2025年度後期のNHK連続テレビ小説第113作として制作されたテレビドラマです。2025年9月29日から放送が開始され、全25週125回の放送が予定されており、2026年3月まで続く見込みとなっています。本作は小泉八雲の妻・小泉セツをモデルとしていますが、原作となる小説や漫画は存在せず、ふじきみつ彦によるオリジナル脚本のフィクション作品として制作されています。音楽は映画やアニメの音楽で高い評価を得ている牛尾憲輔が担当しており、明治時代の雰囲気を表現しながらも現代的なセンスを取り入れた楽曲が特徴となっています。主題歌は男女デュオによる温かみのある歌声で知られるフォークユニット、ハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」で、人生の喜びと悲しみを優しく歌い上げる楽曲がドラマの世界観に寄り添っています。
物語の舞台は明治時代の松江です。主人公の松野トキは、没落士族の娘として生まれ、厳しい環境の中で成長していきます。そんな彼女の人生は、外国人英語教師のレフカダ・ヘブン(小泉八雲がモデル)との出会いによって大きく変わっていきます。トキは、日本の怪談や民話に深い関心を持つヘブンの通訳や助手として働くようになり、やがて二人は結婚します。異文化の中で育った二人が、互いの文化を尊重しながら愛を育んでいく姿が描かれており、ドラマタイトルの「ばけばけ」は妖怪や幽霊が姿を変える「化ける」という言葉を連想させ、八雲の怪談文学との関連を示唆しています。
「ばけばけ」の主要キャスト一覧
ヒロインの松野トキを演じるのは髙石あかりです。彼女は朝ドラ史上3番目に多い2892人のオーディションから選出されました。松江の没落士族の娘という難しい役どころを繊細かつ力強い演技で表現しており、外国人教師との出会いによって人生が変わっていく様子を表情の変化だけで表現する演技力は高く評価されています。
トキの夫となるレフカダ・ヘブン役はトミー・バストウが演じています。国内外1,767人が応募したオーディションから選ばれた逸材で、外国人でありながら日本に深く惹かれていくヘブンの心情を説得力のある演技で表現しています。トミー・バストウは日本語のセリフにも挑戦しており、ハーンが話していたとされる独特の日本語も再現しています。外国人俳優が朝ドラの重要な役を演じることは珍しく、作品の国際性を高める要因となっています。
その他の主要キャストとしては、トキの父・松野司之介役に岡部たかし、トキの母・松野フミ役に池脇千鶴、トキの祖父・松野勘右衛門役に小日向文世が出演しています。また、英語教師の錦織友一役を吉沢亮が演じており、松江出身の秀才で「大盤石」の異名を持つキャラクターを、コミカルな場面とシリアスな場面の両方を巧みに演じ分けています。特にスキップの場面では「下手なスキップ」を演じるという難しい演技に挑戦して話題となりました。武家の当主・雨清水傳役に堤真一、その妻・雨清水タエ役に北川景子、雨清水三之丞役に板垣李光人が出演しており、重厚な演技で物語に深みを与えています。さらに江藤知事役に佐野史郎、江藤リヨ役に北香那、山根銀二郎役に寛一郎と、実力派俳優陣が脇を固めています。
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の生涯
ドラマの重要人物であるレフカダ・ヘブンのモデルとなった小泉八雲について理解することは、夏目漱石との関係性を知る上で欠かせません。小泉八雲の本名はパトリック・ラフカディオ・ハーンで、1850年6月27日にギリシャのレフカダ島で生まれました。父はアイルランド人の軍医、母はギリシャ人でしたが、幼少期に両親が離婚し、アイルランドの大叔母に育てられました。青年期にはイギリスで教育を受けた後、19歳でアメリカに渡り、ジャーナリストとして活動を始めました。シンシナティやニューオーリンズで新聞記者として働き、特に犯罪報道や文芸批評で評価を得ています。
1890年、40歳のときに特派員として来日しました。当初は短期間の滞在予定でしたが、日本の文化と風土に魅了され、そのまま日本に留まることを決意しました。来日後、ハーンは島根県松江市の尋常中学校(現・島根県立松江北高等学校)の英語教師として着任し、松江では没落士族の娘である小泉セツと出会い、1891年に結婚しています。松江での生活は、ハーンにとって日本文化を深く理解するための重要な期間となりました。セツは日本の民話や怪談を語り聞かせ、ハーンはそれらを英語で書き留めていきました。この共同作業が、後の『怪談』などの名作につながることになります。しかし、山陰地方の厳しい冬の寒さはハーンの体調に悪影響を及ぼし、夫妻は1891年11月に松江を離れることになりました。
松江を離れたハーンは、熊本県の第五高等中学校(現・熊本大学)の英語教師として約3年間勤務しました。この時期に執筆された作品には『石仏』『夏の日の夢』『知られぬ日本の面影』『東の国から』などがあります。1896年9月には帝国大学文科大学(現・東京大学文学部)の英文学講師として着任し、大学では英文学や英語を教え、学生たちから絶大な人気を博しました。ハーンの講義は単なる語学教育にとどまらず、文学や文化に対する深い洞察を含んでおり、多くの学生に感銘を与えました。同年、ハーンは日本に帰化し「小泉八雲」という日本名を名乗るようになりました。「八雲」という名前は、古事記に登場する「八雲立つ出雲」という言葉に由来しており、彼が最初に赴任した松江(出雲国)への愛着を示しています。1904年9月26日、小泉八雲は心臓発作により54歳で逝去しました。
夏目漱石の生涯と経歴
夏目漱石(本名:夏目金之助)は、1867年2月9日(慶応3年1月5日)に江戸の牛込馬場下横町(現・東京都新宿区)で生まれました。漱石は夏目家の末っ子として生まれましたが、生後まもなく里子に出され、その後養子に出されるなど、幼少期は波乱に満ちていました。東京帝国大学英文科を卒業後、教職の道に進み、1895年には愛媛県尋常中学校(現・松山東高等学校)の英語教師として赴任しました。この経験が後の小説『坊っちゃん』の題材となっています。
1896年、漱石は熊本県の第五高等学校(五高)の英語教師として赴任しました。興味深いことに、これは小泉八雲が五高を去った後のことであり、漱石は八雲の後任として五高に着任したことになります。熊本での約4年間、漱石は教壇に立ちながら英文学の研究を深めていきました。この時期に俳人・正岡子規との親交も深まり、俳句の創作にも力を入れるようになりました。
1900年、漱石は文部省からイギリス留学を命じられ、ロンドンに渡りました。2年間のイギリス生活は、漱石にとって精神的に苦しい時期でした。異国での孤独感や英文学研究に対する葛藤から、神経衰弱を患うこともありました。しかし、この留学経験は漱石の文学観に大きな影響を与え、帰国後の作家活動の土台となりました。
小泉八雲と夏目漱石の不思議な縁
小泉八雲と夏目漱石の間には、日本文学史上でも特筆すべき奇妙な縁があります。それは、漱石が二度にわたって八雲の後任を務めることになったという事実です。
最初は熊本の第五高等学校です。八雲が1891年に松江から熊本に移り、1894年に神戸へ去った後、その2年後の1896年に漱石が五高に着任しました。直接の後任ではないものの、同じポストを引き継ぐ形となりました。
二度目は東京帝国大学です。1896年に八雲が帝大に着任し、1903年に解雇された後、その直接の後任として漱石が就任しました。この人事には複雑な経緯がありました。当時の文科大学長は、八雲の受け持ち授業を減らして漱石を採用しようとしました。しかし八雲がこれを渋ったため、最終的に八雲を解雇するという決定が下されました。
この決定に対して、学生たちは激しい留任運動を展開しました。八雲の講義を慕っていた学生たちは、「ヘルン先生のいない文科で学ぶことはない」と言って法科に転科する者まで現れました。川田順などは、その代表的な学生の一人です。このような状況の中で後任として着任した漱石に対して、一部の学生は反感を抱いていました。漱石自身もこの状況に苦しみ、大学での講義に困難を感じることがあったといいます。
両者は同じ英文学者・教育者でありながら、その個性は対照的でした。八雲は外国人でありながら日本文化に深く傾倒し、日本の怪談や民話を世界に紹介することに情熱を注ぎました。彼の日本に対する愛情は純粋で、日本人以上に日本を理解しようとする姿勢がありました。一方、漱石は日本人でありながら西洋文学に精通し、近代的な自我の問題を追求しました。イギリス留学で経験した西洋との相克は、彼の文学の重要なテーマとなりました。興味深いことに、二人は同じ時代に同じ場所で活動しながら、ほとんど接点がなかったとされています。しかし、漱石は八雲の著作を読んでおり、その日本文化への見識を尊敬していたという記録が残っています。
「ばけばけ」における夏目漱石の登場可能性
「ばけばけ」は小泉八雲の妻・セツをモデルにしたドラマであり、八雲の生涯における重要な出来事が描かれると考えられます。史実では、八雲が東京帝国大学を解雇され、その後任として夏目漱石が就任するという出来事は、八雲の晩年における大きな転機でした。この出来事がドラマで描かれるとすれば、夏目漱石が登場人物として登場する可能性は十分にあります。
2025年11月25日現在、「ばけばけ」は第9週「スキップ、ト、ウグイス。」が放送されている段階です。物語はまだ松江時代を中心に展開しており、東京帝国大学時代に至るまでにはまだ時間がかかると思われます。全25週125回の放送予定から考えると、東京時代が描かれるのは後半以降になると予想されます。夏目漱石の登場があるとすれば、その時期になる可能性が高いでしょう。
もし夏目漱石が登場するとすれば、どのような形で描かれるのでしょうか。史実では、八雲の解雇と漱石の就任は、八雲にとって非常に辛い出来事でした。学生たちの留任運動にもかかわらず解雇されたことは、八雲の晩年に暗い影を落としました。ドラマでは、この出来事がセツの視点から描かれることになるでしょう。夫の苦悩を支える妻の姿、そして後任者である漱石との関係がどのように描かれるかは、注目すべきポイントです。
夏目漱石役のキャスト発表時期の予想
NHK朝ドラでは、新しいキャストは放送開始後も順次発表されることが多い傾向があります。「ばけばけ」でも、2025年2月から9月にかけて複数回にわたってキャスト発表が行われてきました。夏目漱石役のキャストが発表されるとすれば、東京帝国大学時代のエピソードが放送される前後になると予想されます。
夏目漱石は日本文学史上最も著名な作家の一人であり、その役を演じる俳優には相当のプレッシャーがかかることが予想されます。これまでも映画やドラマで夏目漱石役を演じた俳優は多く、その演技は常に注目を集めてきました。「ばけばけ」においても、著名な文豪を演じるにふさわしい実力派俳優が起用されることが期待されます。
小泉セツの人物像と八雲への貢献
ドラマの主人公のモデルとなった小泉セツについても詳しく見ていきましょう。小泉節子(こいずみ せつこ)は、慶応4年2月4日(1868年2月26日)に出雲松江藩の家臣小泉家の二女として生まれました。生家である小泉家は松江藩に代々仕え、禄高三百石の「上士」と呼ばれる由緒ある家柄でした。幼少期にセツは親戚の稲垣家に養女として出されました。稲垣家の家柄は禄高百石の「並士」であり、小泉家より格式は下でしたが、養父母の金十郎・トミはセツを「オジョ(お嬢)」と呼んで慈しみ、大切に育てました。
明治維新後、稲垣家は没落し、セツは11歳から生家の機織会社で織子として働くことになりました。厳しい生活の中で成長したセツは、18歳の時に婿養子を迎えて結婚しましたが、この結婚生活は長くは続きませんでした。夫は貧しさに耐えられず出奔し、大阪に移ってしまいました。セツは22歳で正式に離婚し、小泉家に復籍することになりました。
離婚後、家計を支えるためにセツは様々な仕事をしました。そんな中、松江の英語教師として赴任したラフカディオ・ハーンの家の住み込み女中として働くことになりました。この出会いがセツの人生を大きく変えることになります。ハーンは当時41歳、セツは23歳であり、18歳の年の差がありました。二人は次第に惹かれ合い、やがて結婚することになりました。
八雲とセツが惹かれ合った理由には、いくつかの共通点があります。八雲は4歳で母と生き別れ、16歳のときには左目を失明し、赤貧生活を経験しました。結婚にも一度失敗しています。セツもまた、幼くして養女に出され、最初の結婚に失敗しています。二人とも辛い経験を重ねてきたからこそ、互いの苦しみを理解し、支え合うことができたのでしょう。また、二人とも物語が大好きで、他者に偏見を持ったり世間体を気にしたりしない性格も共通していました。
興味深いエピソードがあります。セツは幼いころ、軍事教練を見学していた時にフランス人の下士官ヴァレットと出会いました。ほかの子どもたちは初めて見る西洋人を恐れて逃げていく中、セツだけは逃げませんでした。ヴァレットはセツの頭をなで、小さな虫眼鏡をくれました。セツは後に「その出来事がなければ、後年、ラフカディオ・ハーンと結婚することは難しかっただろう」と記しています。
セツは日本語しか話せず、八雲は日本語が十分ではありませんでした。そのため二人は「ヘルンさん言葉」と呼ばれる独特のコミュニケーション方法を編み出しました。これは簡略化された日本語で、二人だけに通じ合う言葉でした。この「ヘルンさん言葉」を通じて、セツは日本の怪談や民話を八雲に語り聞かせました。八雲はそれらを英語で書き留め、独自の文学作品として昇華させていきました。セツは単なる妻ではなく、八雲の文学活動における重要なパートナーだったのです。
八雲とセツの間には三男一女の4人の子供が生まれました。長男の一雄は1893年に生まれ、後にエッセイストとして『父小泉八雲』などの著作を残しています。一家は松江、熊本、神戸、東京と各地を転々としながらも、温かい家庭を築いていきました。八雲は家族を深く愛し、セツは「世界で一番良きママさん」と呼ばれ、八雲を「世界で一番良きパパさん」と呼んでいたといいます。
1904年9月26日、小泉八雲は心臓発作により54歳で逝去しました。セツとともに過ごした13年8ヶ月は、彼女の64年の生涯の中で最も輝いていた時期でした。八雲は遺言状で遺産をすべて妻に譲ることを明言しており、セツは西大久保の家や書斎を生前のまま残し、裕福な暮らしをしながら子供たちを育てることができました。1914年には八雲との思い出をまとめた『思い出の記』が出版されました。セツは晩年、動脈硬化に苦しみ、1932年(昭和7年)2月18日に64歳で死去しました。
小泉八雲の代表作「怪談」の世界
小泉八雲の代表作『怪談』は、1904年に出版されました。この作品集には「耳なし芳一の話」「むじな」「雪女」「ろくろ首」など、日本の伝統的な怪談や民話が収められています。これらの物語は、妻セツが八雲に語り聞かせた民話や伝承が元になっています。セツは松江出身であり、出雲地方に伝わる多くの怪談や民話を知っていました。八雲はそれらを聞き取り、独自の文学的表現で英語に書き直しました。
その他の代表作としては、『知られぬ日本の面影』(1894年)があります。これは日本の風俗や文化を西洋人の視点から描いた紀行文集です。また、『心』(1896年)は日本人の精神性を探求したエッセイ集であり、『日本―一つの解明』(1904年)は日本文化の本質に迫る論考です。これらの作品は、日本文化を西洋に紹介する上で重要な役割を果たし、現在でも世界中で読み継がれています。
ドラマ「ばけばけ」というタイトル自体が、怪談や妖怪を連想させます。ドラマでは、トキがヘブンに怪談を語り聞かせる場面が描かれると予想されます。この共同作業を通じて、二人の絆が深まっていく様子が物語の重要な要素となるでしょう。
「ばけばけ」の視聴率と評判
NHK朝ドラ「ばけばけ」は、2025年9月29日の放送開始以来、安定した視聴率を記録しています。初回の平均世帯視聴率は16.0%で、2020年前期以降の朝ドラでは『あんぱん』(15.4%)に次ぐ2番目の数字でした。その後も視聴率は堅調に推移し、第37回(11月18日放送)では世帯16.2%、個人8.8%を記録し、番組最高の数字となりました。全話平均視聴率は世帯15.2%(第39話まで)となっています。
2025年11月現在、「ばけばけ」の平均視聴率15.1%は、民放ドラマのトップ作品を約5ポイント上回っており、朝ドラとしての強さを示しています。視聴者からの反応は概ね好評であり、「史実に基づきながら、時間を忘れるくらい視聴者を引き付ける配役の演技力や脚本はお見事」という声が上がっています。また、テレビ業界内でも評価が高く、「滅多に他人のドラマを誉めないテレビマンの間でも評判が高い」との報道もあります。
怪談が題材になるはずですが、出足の印象は明るく和やかな人間ドラマで、現代的な会話劇のコメディ要素がふんだんにちりばめられている点が、老若男女に受け入れられている要因と分析されています。一方で、「時代背景が明治時代なのに今風のテンポで進んで違和感を覚える」といった批判的な意見も一部には見られます。
今後の展開と夏目漱石登場への期待
「ばけばけ」は全25週125回の放送予定であり、2025年11月現在、まだ物語の序盤から中盤にかけての段階です。今後、トキとヘブンの結婚、熊本への移住、東京での生活など、多くの出来事が描かれることが予想されます。特に注目されるのは、東京帝国大学時代のエピソードです。ヘブンの大学での活動、学生たちとの交流、そして解雇という悲劇的な出来事がどのように描かれるかが、物語の後半の大きな見どころとなるでしょう。
史実における小泉八雲と夏目漱石の関係を考えると、ドラマでも夏目漱石が登場する可能性は十分にあります。もし登場するとすれば、どのような俳優が演じるのか、また両者の関係がどのように描かれるのかは、視聴者にとって大きな関心事です。NHKからはまだ夏目漱石役のキャスト発表はされていませんが、今後の発表に期待が高まっています。
「ばけばけ」は、エンターテインメントとしてだけでなく、明治時代の文学史を学ぶ機会としても価値があります。小泉八雲という人物を通じて、明治時代の日本と西洋の文化交流、外国人から見た日本の姿、そして当時の文学者たちの活動を知ることができます。夏目漱石が登場することになれば、日本近代文学の成立過程をより深く理解する機会にもなるでしょう。両者の対比を通じて、明治文学の多様性と豊かさが浮かび上がってくることが期待されます。
夏目漱石の作家としての業績
漱石は大学講師として働きながら、作家としての活動を本格化させていきました。1905年に発表した『吾輩は猫である』が大きな反響を呼び、続いて『坊っちゃん』『草枕』などの傑作を次々と発表しました。1907年には大学を辞職し、朝日新聞社に入社しました。専業作家として『三四郎』『それから』『門』の前期三部作、『彼岸過迄』『行人』『こころ』の後期三部作など、日本近代文学を代表する作品を生み出しました。1916年12月9日、漱石は胃潰瘍の悪化により49歳で逝去しました。
八雲と漱石は、両者とも日本文学史において重要な位置を占めています。八雲は日本文化を世界に紹介した功績が大きく、「怪談」という日本独自のジャンルを世界文学の中に位置づけました。漱石は日本近代文学の礎を築き、現代に至るまで多大な影響を与え続けています。
明治時代の文学者たちと英語教育
明治時代(1868年から1912年)は、日本文学にとって大きな転換期でした。西洋文学の影響を受けながら、日本独自の近代文学が形成されていった時代です。この時代には、小泉八雲や夏目漱石のほかにも、森鷗外、二葉亭四迷、樋口一葉、泉鏡花など、多くの重要な作家が活躍しました。彼らは西洋と日本の文化の間で葛藤しながら、新しい文学の形を模索していきました。
小泉八雲のように日本に帰化した外国人作家の存在は、明治文学において特異な位置を占めています。彼らは外部者の視点から日本を見つめ、日本人には気づきにくい日本文化の本質を浮かび上がらせました。八雲の作品は、日本人読者にとっても新鮮な発見をもたらすものであり、自国の文化を見直すきっかけとなりました。このような「外からの視点」は、現代においても重要な意味を持っています。
明治時代には、英語教師として活動しながら文学活動を行う作家が多くいました。八雲も漱石も、まず英語教師としてのキャリアを築き、その後文学者としての名声を得ていきました。この時代、英語教育は西洋文明を取り入れるための重要な手段と考えられており、英語教師は高い社会的地位を持っていました。八雲や漱石のような優れた英語教師は、教え子たちに大きな影響を与え、次世代の文学者や知識人を育てる役割も果たしました。
まとめ
NHK朝ドラ「ばけばけ」は、小泉八雲の妻・セツをモデルにした物語であり、異文化間の愛と理解をテーマにした作品です。史実では、小泉八雲と夏目漱石は不思議な縁で結ばれており、漱石は二度にわたって八雲の後任を務めることになりました。特に東京帝国大学における後任人事は、八雲の晩年に大きな影響を与えた出来事でした。
2025年11月25日現在、ドラマにおける夏目漱石の登場は確認されておらず、キャスト発表もされていません。しかし、物語の後半で東京帝国大学時代が描かれる際に登場する可能性は十分に考えられます。今後のNHKからのキャスト発表や物語の展開に注目していきましょう。
「ばけばけ」を通じて、明治時代の日本と西洋の文化交流、小泉八雲の文学世界、そして夏目漱石との関係について、多くの視聴者が関心を持つきっかけとなることが期待されます。髙石あかり演じるトキとトミー・バストウ演じるヘブンの物語が、今後どのように展開していくのか、引き続き見守っていきたいものです。




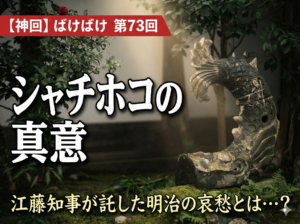


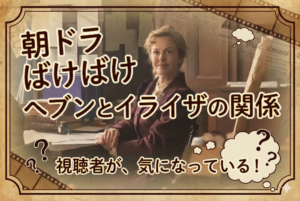
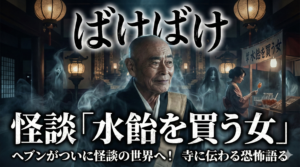

コメント