斬新な静止画で話題を集めたオープニング映像の評価
9月29日に放送が始まったNHK連続テレビ小説「ばけばけ」では、これまでの朝ドラとは一線を画す試みが行われた。夫婦フォークデュオであるハンバートハンバートが歌う「笑ったり転んだり」をバックに、写真家の川島小鳥氏が撮影した主人公夫婦の静止画が次々と映し出されるという構成だ。従来の朝ドラで見られたような動画を使った映像ではなく、完全に写真のみで構成されたオープニングは、視聴者に新鮮な驚きを与えた。
公式の説明によれば、静止画を採用した理由は視聴者に想像の余地を与えたいという制作側の意図があったという。画面左側にはトキとヘブンの仲睦まじい姿を切り取った夫婦写真が配置され、まるで結婚式のエンディングムービーや前撮り写真を見ているかのような温かさが感じられる。自然光を活かした美しい撮影技術と、ゆったりとした主題歌のメロディが相まって、朝の時間帯にふさわしい穏やかな雰囲気を醸し出している。
視聴者からは「二人のスナップ写真で、旦那さんが写真でも奥さん見つめてるのが多くて心温まる」「完全に結婚式のエンディングのようでボロボロ泣いてしまった」といった好意的な声が多数寄せられた。写真切り替えだけというシンプルな構成に驚きながらも、その雰囲気の柔らかさと曲の温かさに涙する視聴者も少なくなかった。従来の朝ドラテイストを保ちながらも、映像が主演夫婦のスナップ写真という点が地味に攻めているという評価もあり、新しい朝ドラのスタートに期待を寄せる声が多く見られた。
一方で、斬新なようで手抜きのようだという意見や、もう少し予算と時間をかけて制作すべきだったという批判的な声も存在する。特に大阪制作の朝ドラは東京制作に比べて予算が限られているという指摘もあり、外部発注のCGを多用した東京制作の方が見応えがあるという比較論も出ている。スチール写真の縦横比が見慣れたものと違うことへの違和感や、奇をてらわず普通に写真と字幕をオーバーラップさせた方が良かったという意見もあった。
しかし、過去の朝ドラでも初回のオープニングに対しては賛否両論があり、回を重ねるごとに視聴者が慣れていくという傾向がある。前作「あんぱん」でも当初は主題歌が作品に合わないという批判を受けていたが、最終的には有終の美を飾った。朝ドラは最終話まで視聴してこそ真価が問われるものであり、「ばけばけ」のオープニングも今後本編に馴染んでいくことが期待されている。写真というメディアの持つ静かな力と、夫婦の物語を丁寧に描こうとする制作陣の姿勢は、半年間の放送を通じて視聴者の心に深く刻まれていくのではないだろうか。
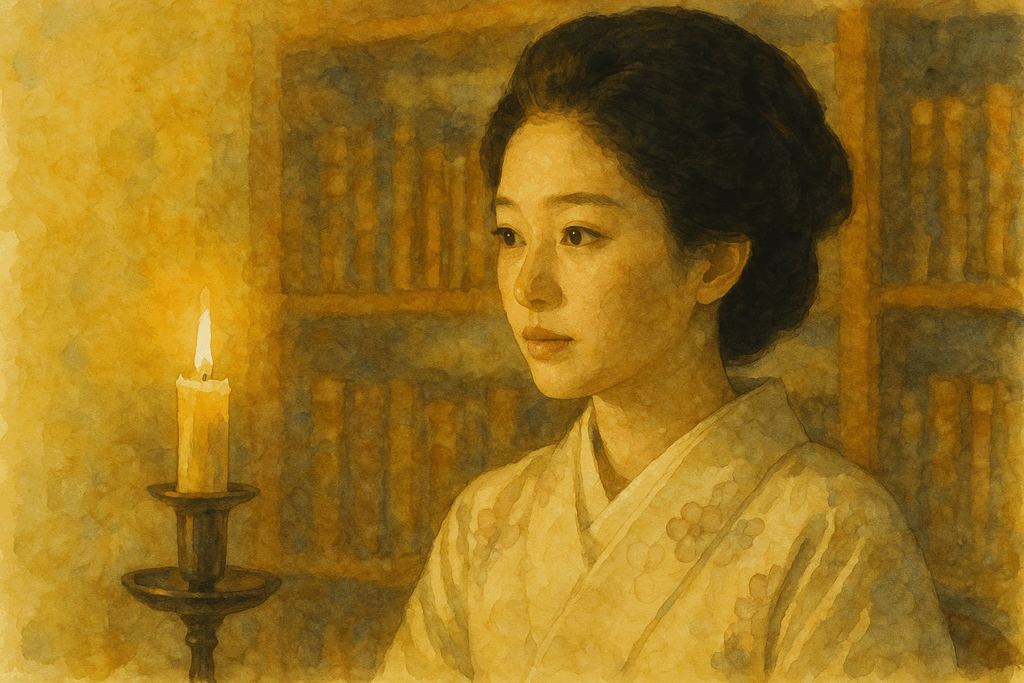
視聴者から指摘が殺到したクレジット表記の問題点
「ばけばけ」のオープニング映像で最も多くの指摘を集めたのが、キャストやスタッフのクレジット表記の文字サイズだった。画面右側に表示されるクレジットは、前作「あんぱん」と比較しておよそ2分の1程度の大きさしかなく、多くの視聴者が「読めない」「小さすぎる」という不満を表明した。特に朝ドラの視聴者層にはシニア世代が多く、老眼や視力低下に悩む方々にとっては、テレビのすぐ近くまで行かなければ文字が判読できないという深刻な問題となっている。
SNS上では「タイトルの字幕が小さすぎて読めない。初っ端からストレス溜まる」「キャスト欄の文字小さすぎておばさんには見えづらい」といった声が相次いだ。雰囲気は良い感じでオープニングもおしゃれだが、おしゃれであるがゆえにクレジットの文字がかなり小さく、NHKらしからぬ挑戦的な姿勢だという指摘もあった。老若男女に向けた放送を行うNHKとしては、デザイン性を重視するあまり視認性を犠牲にしてしまったのではないかという疑問の声が上がっている。
朝ドラ終了直後の情報番組「あさイチ」でも、MCの博多華丸が「あえてでしょうけど、書いてある名前がすごい小さくて。全国のおじいちゃんおばあちゃんが、こう……」と言いながら画面に顔を近づけるポーズを取り、文字サイズの問題に言及した。これは視聴者の多くが感じていた違和感を代弁するものであり、番組内でのこの発言に共感する声も多数寄せられた。デザイナーの視点からも、写真のイメージに合わせて雑誌風の垢抜けた印象を狙った結果だろうが、文字は読めないと意味がないという指摘があった。
朝ドラを楽しみにしている視聴者にとって、オープニングのクレジットを見て今日は誰が出演するかを確認することも重要な楽しみの一つだ。前作「あんぱん」では「今日はこの人が出る」「またあの人が出る」といった期待感を持ちながら本編を迎えることができたが、「ばけばけ」では文字が小さすぎて誰が何という役で出るのかすらわからないまま本編に入ってしまうという不満が出ている。朝ドラに出演することを夢見ていた俳優やその親類縁者にとっても、画面を食い入るように見て名前を確認したいという思いがあるはずで、せっかくのキャストの字幕が小さいのはもったいないという声もあった。
高齢者の中には、白地に文字が書いてあると光って見えづらいという視覚的な問題を抱えている方も多い。タイトルクレジットだけでなく、ドラマの途中で出てくる手紙なども文字が光って見づらく、スマホの画面の文字も判読できないという切実な訴えもあった。できれば白地の部分が多いので文字に色をつけて大きくしてほしいという要望も出ており、視聴環境の改善が求められている。一部では、放送中に出演者の文字だけでも大きく変更してほしいという具体的な要望も寄せられており、制作側の早急な対応が期待されている状況だ。
ゆったりとした主題歌が生み出す新しい朝ドラの雰囲気
夫婦フォークデュオのハンバートハンバートが歌う「笑ったり転んだり」は、従来の朝ドラ主題歌とは異なる穏やかで落ち着いた印象を与えている。前作「あんぱん」のRADWIMPSによる「賜物」が、スピード感あふれる独特のメロディラインで朝からチャカチャカした曲調だったのに対し、「ばけばけ」の主題歌はゆったりとしたテンポで、明治時代という作品の時代背景にも合致した雰囲気を持っている。この曲調の変化は、視聴者に新鮮な印象を与えると同時に、朝ドラの多様性を示すものとなった。
主題歌に対する視聴者の反応は概ね好意的で、「曲の温かさがじわじわとしみてまだ何も知らないのに涙目になった」「なんだか映画を観ているような気分になった」といった声が寄せられている。ゆったりと流れる音楽が、川島小鳥氏が撮影した美しい写真と相まって、朝の時間帯に癒しを提供している。シンプルで穏やかなオープニングは、ドラマの時代背景に合わないCGに半年間うんざりしていた視聴者からも歓迎されており、作品の世界観を丁寧に表現していると評価された。
ただし、ハンバートハンバートというアーティスト選択については、一部で懸念の声も上がっている。個人的には大好きな夫婦デュオでドラマに合っている素敵な主題歌だという意見がある一方で、ここ10年の朝ドラ主題歌を歌ってきたアーティストと比較すると、少しマイナーすぎるのではないかという心配も存在する。しかし、マイナーであるからこそ新鮮味があり、作品の雰囲気に寄り添った選択だったという見方もできるだろう。
朝ドラの主題歌は、最初は馴染めなくても回を重ねるごとに視聴者の心に定着していくという傾向がある。前作「あんぱん」も当初は主題歌が作品に合わないという批判を受けていたが、じわじわとこの曲で良かったと思えるようになり、最終的には多くの視聴者に受け入れられた。統計学どうこうの歌詞は覚えられないまま最終回を迎えたという声もあったが、それでも作品と共に歩んだ楽曲として記憶に残っている。「ばけばけ」の主題歌も同様に、半年間の放送を通じて視聴者の日常に溶け込んでいくことが期待される。
主題歌の傾向がガラッと変わったことで、高齢者層は引き続き視聴するだろうが、若年層は前作から後退する可能性があるという指摘もある。しかし、朝ドラは幅広い年齢層に向けた作品であり、時には落ち着いた楽曲で心を癒すことも重要だ。歌はまあ慣れたら何とも思わなくなるという声もあり、最初の印象だけで判断せず、作品全体を通して主題歌を味わうことが大切だろう。「あんぱんロス」を感じていた視聴者も、半年後には「ばけばけロス」を感じられる良作になることを期待する声が多く寄せられている。
阿佐ヶ谷姉妹と小泉八雲の世界観が融合した物語の始まり
「ばけばけ」の初回放送で大きな注目を集めたのが、お笑いコンビの阿佐ヶ谷姉妹によるナレーションだった。渡辺江里子が蛇の声を、木村美穂が蛙の声を担当し、トキとヘブンの庭に住む2匹の動物として、夫婦の歩みを優しく見守るという役どころだ。冒頭から「蛇です。蛙です。2匹合わせて蛇と蛙です」とテンポよく挨拶し、「おトキさんがヘブンさんに語る怪談を聞いては、夜な夜な震え上がっているのよねぁ」「こう見えて私達、怖がりなのよ」と2匹の掛け合いが繰り広げられた。
この斬新な演出に対して、視聴者からは「蛇と蛙の掛け合い最高すぎる」「いきなり動物が喋りだしてびっくりした」「阿佐ヶ谷姉妹だったんだ。納得の掛け合いだわ」といった反響が寄せられた。納得のコンビネーションでぴったりのキャスティングだという評価もあり、これから2匹の掛け合いを楽しみにする声も多い。蛇と蛙という一見不気味にも思える組み合わせが、阿佐ヶ谷姉妹の軽妙なトークによってコミカルな魅力を持つキャラクターとして成立している点が評価されている。
一方で、阿佐ヶ谷姉妹の起用には批判的な意見も存在する。蛇と蛙の語りというアイデア自体は面白いが、少し喋りすぎだったという指摘や、蛇と蛙のどちらが喋っているのか分からないのに台詞が多すぎて面白さが伝わりにくいという声もあった。かといってアップにもし辛いという演出上の制約もあり、バランスの難しさが浮き彫りになっている。前作「あんぱん」のナレーションは非常に少ないが効果的で、林田理沙アナウンサーの声に魅了された視聴者からすると、今回の漫才風のナレーションは受け入れるのに時間がかかるという意見もあった。
また、蛇と蛙という動物の選択自体に抵抗を感じる視聴者も少なくない。朝から蛇とカエルが出てきて気持ち悪くなってすぐテレビを消したという声や、ヘビが嫌いなので出すなら可愛くデフォルメしてほしいという要望も寄せられている。怪談をテーマにした作品である以上、多少の不気味さは作品の雰囲気を演出する要素として必要だが、朝の時間帯に視聴する作品としては配慮が必要だという指摘は理解できる。阿佐ヶ谷姉妹の蛙と蛇は必要ないのではないか、前作同様にアナウンサーのナレーションで良くないかという意見もあった。
物語の中心となる小泉八雲は、日本の民話を「怪談」という名の文学作品へ昇華し世界へ広めた明治時代の小説家だ。初回では、トキがヘブンに「耳なし芳一」を聞かせるシーンから始まり、盲目の琵琶法師が平家の怨霊に気に入られ、身体中にお経を書かれて守られたものの耳に書き忘れがあったために耳だけを引きちぎられるという日本の怪談が語られた。いきなり耳なし芳一のグロい話かよ、これからもたびたび朝から古い怪談を聞かされると思うときついという声もあるが、怪談を愛する夫婦の物語である以上、避けては通れない要素だろう。冒頭から高石あかりの演技がすごいことがわかるという評価もあり、主人公の高石をはじめとするキャストたちの演技やストーリーに期待する声も多い。今後、阿佐ヶ谷姉妹による蛇と蛙がどのように主人公達の行く末に寄り添っていくのか、期待して観ていく価値はあるだろう。




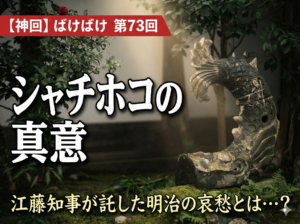


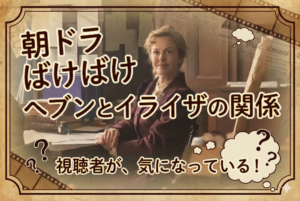
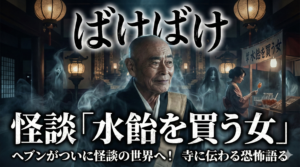

コメント