2025年秋から放送予定のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、松江の没落士族の娘・小泉セツと、ギリシャ生まれの作家ラフカディオ・ハーン(後の小泉八雲)の奇妙で温かな夫婦生活を描く物語です。本作において視聴者の関心が高いのが「料理監修は誰なのか」という疑問ではないでしょうか。結論から申し上げますと、2025年11月現在、NHKから公式な料理監修者の発表はまだ行われていません。しかし、過去のNHK大阪放送局制作の朝ドラの傾向から分析すると、辻調理師専門学校(辻調グループ)が技術監修の中核を担い、松江の郷土料理については地元の食文化専門家や老舗和菓子店が協力する「ハイブリッド体制」が採用される可能性が極めて高いと考えられます。本作では、セツがハーンのために作る西洋料理と、松江の伝統的な和食の両方が重要な役割を果たすため、料理監修は単なる技術指導を超え、異文化コミュニケーションの象徴として機能することが予測されます。

「ばけばけ」の料理監修体制を徹底予想
NHK連続テレビ小説における料理監修は、近年「チーム制」あるいは「多層的監修」の傾向が強まっています。特に「ばけばけ」のような明治時代を舞台とした時代劇であり、かつ異文化交流を軸とする作品では、一人の料理家がすべてを担当することは現実的ではありません。ここでは、本作で想定される監修体制について詳しく分析していきます。
NHK大阪放送局の制作特性と辻調グループの関与
「ばけばけ」はNHK大阪放送局(通称BK)の制作です。過去のBK制作朝ドラを振り返ると、料理が重要な要素となる作品において、辻調理師専門学校が技術監修の中核を担ってきた歴史があります。2013年放送の「ごちそうさん」では大正から昭和初期の家庭料理と洋食の再現が行われ、2018年の「まんぷく」ではインスタントラーメン開発の技術的指導を含む監修が実施されました。2020年の「おちょやん」では大阪の仕出し屋や家庭料理の再現が行われ、2023年の「ブギウギ」では戦後の洋食や屋台料理などが忠実に再現されています。
辻調理師専門学校は、西洋料理部門と日本料理部門の両方を持つ日本最大級の料理教育機関です。「ばけばけ」では、セツがハーンのために作る西洋料理(クリスマスプディングやビフテキなど)と、松江の伝統的な和食(シジミ汁やスズキの奉書焼きなど)の双方が登場することが予想されるため、両分野に精通した辻調グループが技術監修として参加する可能性は非常に高いと言えます。
フードスタイリストの役割
技術監修とは別に、実際の撮影現場で料理の見栄えを整えるフードスタイリストの存在も重要です。BK制作の朝ドラでは、広里貴子氏のようなBK制作に精通したフードスタイリストが現場のスタイリングを担当するケースが多く見られます。「ばけばけ」においても、辻調グループが提供するレシピや技術指導に基づき、撮影現場ではフードスタイリストが実際の料理を美しく仕上げる「役割分担」が行われると予測されます。
松江の食文化を支える地域専門家たち
物語の舞台となる島根県松江市は、「不昧公(ふまいこう)」こと松平治郷の影響を受けた茶の湯文化と、宍道湖の七珍(しっちん)で知られる食の都です。これらを正確に描写するためには、地元の食文化に精通した専門家の協力が不可欠となります。
松江は京都、金沢と並ぶ日本三大菓子処として知られており、劇中に登場する和菓子の監修には、彩雲堂や風流堂といった実在の老舗和菓子店が協力する可能性が高いと考えられます。特に松江を代表する銘菓「若草」や「山川」が劇中に登場する際には、その製法や歴史的背景について専門的な指導が行われるはずです。また、島根県や松江市の観光協会がロケ支援および方言指導とセットで、郷土料理の時代考証を行うことも想定されます。宍道湖のシジミ漁の様子や、明治期の漁法、食材の流通に関しては、地元郷土史家の監修が入ることで、より史実に忠実な描写が可能になります。
ラフカディオ・ハーンの食の好みと妻セツの奮闘
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の食の好みは、ドラマにおいてコメディリリーフであると同時に、夫婦愛を象徴する感動的な要素となることが予想されます。ハーンは西洋人でありながら、西洋文明(特にキリスト教的価値観や物質主義)を嫌い、日本の精神性を深く愛した人物でした。しかし、彼の胃袋は正直に西洋の味を求めたという矛盾が、妻セツの苦労の源泉となったのです。
ビフテキへのこだわり
ハーンが特に好んだ料理の一つがビフテキ(ビーフステーキ)です。明治20年代の松江において、牛肉を入手することは非常に困難でした。仏教色が強い地方都市では、四つ足の動物を食べることは依然として忌避される傾向にあったからです。当時は網焼きか、あるいはすき焼き風の調理法が主流でしたが、ハーンは分厚いステーキを好みました。
セツが鍛冶屋に頼んで特注の焼き網や鉄板を作らせたり、遠方の肉屋まで買い出しに行ったりしたエピソードは、夫婦愛の象徴として描かれる可能性が高いでしょう。味付けについては、醤油ベースか、あるいは当時輸入され始めていたウスターソース(リーペリンソースなど)を使用したかが注目点となります。ハーンはウェルダンを好み、大量のジャガイモを添えて食べることを楽しんだと伝えられています。
プラム・プディングの再現という挑戦
ハーンの故郷であるアイルランドやイギリス文化圏の味として、彼が「この世で最も美味なるもの」として愛したのがプラム・プディング(クリスマスプディング)です。本来は牛脂(スエット)、ドライフルーツ、ブランデー、パン粉などを混ぜて長時間蒸し上げる重厚な菓子であり、バターやオーブンがない明治の松江の台所で再現することは、まさに至難の業でした。
セツがいかにしてこの異国の味を再現したかは、ドラマのクライマックスの一つになり得る「発明」の物語です。おそらく和釜での蒸し調理を駆使し、日本で手に入る材料で代用しながら、試行錯誤を重ねたことでしょう。失敗を繰り返しながら、夫のために異国の味を再現しようとするセツの姿は、朝ドラの王道テーマである「食を通じた家族の絆」を体現するものとなるはずです。
ハーンが愛したその他の食べ物
ビフテキやプラム・プディング以外にも、ハーンが好んだ食べ物は数多くあります。松江の天然鰻はハーンのお気に入りの一つであり、宍道湖で獲れる上質な鰻を蒲焼きにして食べることを楽しみました。また、冬になるとこたつに入ってみかんを食べることを好んだという記録も残っています。夏には縁側でスイカを食べることを楽しんだとも伝えられており、こうした「日本の日常」を愛するハーンの姿が、ドラマでも描かれることでしょう。
松江の食文化と宍道湖七珍
「ばけばけ」の舞台となる松江は、豊かな食文化を持つ城下町です。特に宍道湖七珍(しんじこしっちん)と呼ばれる七種類の名産品は、ドラマの中で重要な役割を果たすことが予想されます。
宍道湖七珍とは
宍道湖七珍とは、宍道湖で獲れる七種類の代表的な魚介類を指します。スズキ、モロゲエビ、ウナギ、アマサギ(ワカサギ)、シラウオ、コイ、シジミの七種類で、頭文字を取って「スモウアシコシ」と覚えられています。これらの食材は、明治時代のハーンの食卓にも登場したはずであり、ドラマでも季節ごとに美しく描かれることでしょう。
特にシジミ汁は、松江の朝の象徴として重要な役割を果たします。朝霧の中、シジミ売りの行商人の声と共に登場するシジミ汁は、ハーンが「日本の音」として愛した行商の声とセットで描かれる可能性があります。宍道湖産の大和シジミは、汽水湖という独特の環境で育つため、身が大きく味が濃厚なのが特徴です。
スズキの奉書焼き
スズキの奉書焼きは、不昧公好みの料理として知られる松江を代表する郷土料理です。新鮮なスズキを奉書紙で包んで蒸し焼きにする調理法で、魚の旨味を逃さず、上品な味わいに仕上がります。重要な来客(県知事や宣教師など)をもてなす「晴れの日」の料理として、ドラマでも登場することが予想されます。
ボテボテ茶という庶民の味
ボテボテ茶は、松江の庶民が親しんできた独特の飲み物です。泡立てた番茶の中に、赤飯、煮豆、漬物などを入れて食べる間食であり、労働の合間の休息や、近隣住民との井戸端会議のシーンで登場することが考えられます。質素でありながらも豊かな食文化の象徴として、セツの日常生活を彩る要素となるでしょう。
松江の和菓子文化
松江は京都、金沢と並ぶ日本三大菓子処として知られています。これは、茶人大名として名高い松平不昧公の影響によるものです。不昧公は茶の湯を愛し、茶菓子の発展に大きく貢献しました。その伝統は現代まで受け継がれており、松江には老舗の和菓子店が数多く存在します。
銘菓「若草」と「山川」
松江を代表する銘菓として知られる「若草」は、求肥(ぎゅうひ)に若草色の寒梅粉をまぶした上品な菓子です。もう一つの銘菓「山川」は、紅白の落雁で、不昧公が好んだと伝えられています。これらの和菓子がドラマに登場する際には、その製法や歴史的背景について、地元老舗和菓子店の監修が入ることが予想されます。
茶の湯文化と食の関係
松江における茶の湯文化は、単なる趣味の域を超え、市民生活に深く根付いています。ハーンもまた、日本の茶の湯に深い関心を寄せており、その精神性に惹かれたとされています。ドラマでは、セツが茶を点て、季節の和菓子を添えてハーンをもてなす場面が描かれる可能性があり、この場面においても和菓子監修の専門家の協力が不可欠となるでしょう。
明治時代の台所事情と調理の苦労
「ばけばけ」の時代背景をより深く理解するためには、明治20年代の台所事情について知ることが重要です。当時の調理環境は現代とは大きく異なり、セツの料理への献身がいかに大変なものであったかが見えてきます。
熱源としてのカマド
明治20年代の松江では、ガスはまだ普及しておらず、カマド(へっつい)が主要な調理設備でした。薪や炭を熱源とし、火加減の調整には熟練の技を要しました。西洋料理の調理においては、一定の温度を保つことが重要ですが、カマドでこれを実現するには相当な経験と勘が必要でした。セツが顔を煤だらけにして火を吹く描写は、彼女の献身を視覚的に伝える印象的なシーンとなることでしょう。
水の確保と重労働
水道が普及していなかった当時、水は井戸から汲み上げる必要がありました。水汲みは重労働であり、特に西洋料理は油汚れなど洗い物が多いため、セツの家事負担は相当なものであったと推測されます。また、清潔な水を確保することの難しさは、調理そのものにも影響を与えました。
食材の流通と入手の困難さ
明治中期は、鉄道網の発達により食材の移動距離が伸びた時期ですが、山陰地方は鉄道の開通が遅れたため、松江は独自の食生態系を維持していました。西洋野菜であるキャベツ、玉ねぎ、トマトなどはまだ一般的ではなく、セツはネギや大根、和の柑橘類を駆使して、西洋料理の風味を模索したと考えられます。この「代用食材の工夫」は、現代の視聴者にも共感を呼ぶ要素となるでしょう。
「食」が象徴する異文化コミュニケーション
「ばけばけ」において、料理は単なる生活描写を超え、異文化コミュニケーションの中核をなす重要な要素として機能します。セツは英語が話せず、ハーンは日本語が不完全でした。二人のコミュニケーションにおいて、言語の欠落を埋めたのが「料理」だったのです。
言語を超えた愛情表現
料理は、言葉を超えた愛情伝達手段として機能します。セツがハーンの故郷の味であるプラム・プディングを作ろうとすることは、彼のアイデンティティを肯定する行為であり、ハーンがシジミ汁を愛することは、セツのルーツを受け入れる行為です。この「相互受容のメタファーとしての食」という視点は、ドラマを観る上で非常に重要なテーマとなります。
民藝としての食
ハーンの視点は、後の柳宗悦らの「民藝運動」に通じるものがあります。彼は華美な宮廷料理ではなく、名もなき民衆の日常食に美を見出しました。ドラマ内の料理は、高級な「美食」ではなく、使い込まれた漆器や陶器に盛られた「生活の糧」として美しく撮影されることでしょう。料理そのものだけでなく、それを盛る器や、食事をする空間(陰影礼賛的な薄暗い日本家屋)の美しさにも注目して観ると、より深くドラマを楽しめるはずです。
「ばけばけ」のタイトルと食の関係
タイトル「ばけばけ」が示唆する「化け物」「怪談」の要素は、食文化とも密接にリンクしています。ハーンは怪談の蒐集家として知られており、日本各地の怪異譚を収集し、作品として世に送り出しました。その中には、食にまつわる怪談も数多く含まれています。
お盆の供え物と死者への食事
ハーンは『知られぬ日本の面影』の中で、盆踊りや精霊棚の風習を詳細に記録しています。死者のために用意される食事(影膳)や、白玉団子、季節の果物の描写は、彼が日本人の霊性を理解する入り口となりました。ドラマでも、お盆の時期にセツが先祖のために供え物を準備する場面が描かれる可能性があり、ハーンがその光景を興味深く観察する姿が見られるかもしれません。
食にまつわる禁忌と迷信
当時の松江では、狐や狸に化かされるという迷信と結びついた食べ合わせや、特定の日に食べてはいけないものなどの伝承が語り継がれていました。セツからハーンへ語られる「食の怪談」として、こうした民間伝承がドラマに取り入れられる可能性があります。
季節ごとの食卓風景
「ばけばけ」は秋から放送開始予定であり、ドラマの進行に合わせて季節の食材が登場することが予想されます。松江の豊かな四季と、それに応じた食卓の変化は、ドラマの重要な見どころとなるでしょう。
春の食卓
春には白魚(シラウオ)が旬を迎えます。宍道湖で獲れる白魚は透明感のある美しい魚で、卵とじや吸い物として食されます。また、松江では明治時代にすでにイチゴの栽培が始まっていた可能性があり、珍しい果物としてハーンの食卓に登場するかもしれません。
夏の食卓
夏には鰻が旬を迎えます。松江の天然鰻はハーンのお気に入りであり、土用の丑の日には蒲焼きが食卓に並んだことでしょう。また、天然スズキも夏が旬であり、刺身や塩焼きとして楽しまれました。暑気払いとしてボテボテ茶を飲む場面も描かれるかもしれません。
秋の食卓
秋にはスズキの奉書焼きや栗菓子が登場します。不昧公好みの料理として知られる奉書焼きは、秋の宴席にふさわしい料理です。また、栗を使った和菓子は茶の湯の席で供される上品な菓子であり、松江の秋を彩ります。
冬の食卓
冬にはカモ(鴨肉)が登場します。宍道湖周辺は渡り鳥の飛来地であり、冬にはマガモなどが飛来します。カモ鍋は冬の贅沢な料理として、特別な場面で登場するかもしれません。また、温かいシジミ汁は冬の朝食の定番であり、身体を芯から温めてくれます。出雲地方独特の雑煮も、お正月の場面で描かれることでしょう。
料理監修の重要性と視聴者への影響
「ばけばけ」における料理監修は、単なる技術指導の枠を超え、歴史考証、地域振興、そしてドラマの主題である「他者理解」を支える重要な役割を担っています。視聴者は、画面に映る料理を通じて、明治時代の生活や、セツとハーンの愛情を感じ取ることになります。
時代考証としての料理
明治20年代の台所を正確に再現するためには、当時の調理器具、食材、調理法について詳細な時代考証が必要です。現代では当たり前に使われている調味料や器具が、当時は存在しなかったり、非常に高価だったりしました。料理監修者には、こうした時代背景を踏まえた上で、視覚的にも美しく、かつ史実に忠実な料理を提案することが求められます。
地域振興への貢献
朝ドラの舞台となった地域は、放送期間中に観光客が増加する傾向があります。「ばけばけ」においても、劇中に登場する松江の郷土料理や和菓子が全国的に注目を集めることが予想されます。料理監修を通じて、松江の食文化が正確かつ魅力的に描かれることで、地域振興にも大きく貢献することになるでしょう。
放送開始に向けた期待
2025年秋の放送開始が待たれる「ばけばけ」は、料理を通じた異文化コミュニケーションという普遍的なテーマを描く作品となります。主演の高石あかりさんがセツ役として、どのように明治時代の台所に立ち、ハーンのために奮闘する姿を演じるのか、今から期待が高まります。
料理監修者の正式発表は、放送開始が近づくにつれて行われることが予想されます。しかし、過去の制作実績から推測される「辻調グループと地域専門家のハイブリッド体制」という監修形態は、西洋料理と日本料理の両方が重要な役割を果たす本作にとって、最も適した体制であると言えるでしょう。
放送が始まったら、毎回登場する料理が「セツからハーンへのラブレター」であることを意識して観ると、より深くドラマを楽しめるはずです。言葉が通じなくても、心が通じ合う。その象徴としての「食」の物語に、ぜひご注目ください。


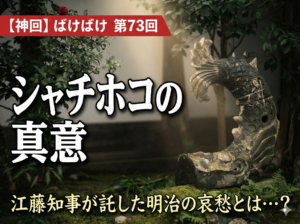


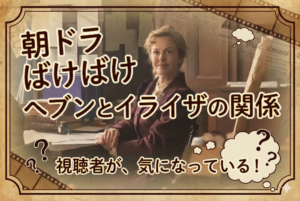
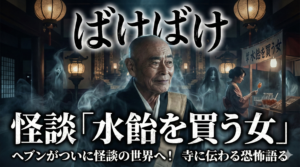



コメント